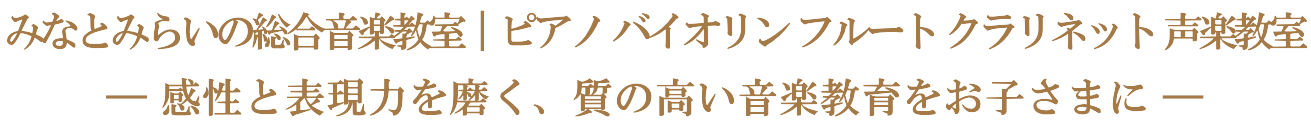ヴァイオリン演奏時の姿勢、楽器の持ち方
華やかな音色と情緒豊かな表現力を併せ持つヴァイオリン。ソロからアンサンブル、オーケストラまで大活躍の楽器ですが、その演奏姿勢も美しくエレガント。「楽器の女王」と呼ばれる理由がここにも垣間見えますね。
弦の振動を駒を介して表板、魂柱を通じて裏板にまで伝達させ、胴体で響きを増幅させることによって、アコースティック楽器にもかかわらずまるで拡声器が持つ性質のように、広がりのある遠くまで通る音色を奏でることができます。
このような理にかなった構造の楽器が、16世紀イタリアで発明され今日まで普及していること、また、楽器自体もニコロ・アマティやガスパロ・ダ・サロなどの400年近い昔に造られたものが大切に後世に伝えられ、残されてきた...。まさに人類の宝、文化芸術遺産とも言える、ロマンあふれる楽器ですね。
拡声増幅器としてのヴァイオリンの性能を最大限に発揮するには、どのような弾き方・弾き姿勢が功を奏するでしょうか?ヴァイオリニストなら常に考え、試行錯誤して探求するテーマです。
ヴァイオリンの持ち方・構え方のチェックポイント
部分の振動を楽器の隅々にまで伝達させて豊かな響きを生み出すためには、まず振動の発生起点となる「弦の振動」を最大にすることが大切です。擦弦楽器であるヴァイオリンにとって、弓と弦の接点に生まれる摩擦力を最大にして、弦の振幅を大きくするためには、以下の点を考慮する必要があります。
- 弦と弓が直角(駒と平行)になる位置関係で楽器を構える
- 振動のロスを生じさせないために、楽器の水平方向の角度を維持する
- 各弦での理想的な楽器の傾き具合を柔軟に調整する
以下、これらのトピックについて順番に紹介していきます。
弦と弓が直角(駒と平行)になる位置関係で楽器を構える
まず、弦と弓が直角(90度)でコンタクトする状態を保つ必要があります。これは駒と弓が平行になるフォームと同じことで、弓で弦をしっかりと捉え摩擦をロスなく生み出すために、最も大切なことです。直角のフォームを実現するためには、「弓を弦に対して直角」させる考え方と、「弦を弓に対して直角」させる2つのパターンの考え方があります。
左右両方の腕の開き具合は、身体の中心線に対して「45度程度」が基本的な構え方になります。これをオーソドックスとして、左右微妙に意図的に角度を変えた構え方など、各々の奏者が経験の中から最も自然で無理の少ない演奏が実現できる角度を見出し、取り入れていく部分になります。
*小さなお子さまにとっても、これはとても大切なポイントになります。初めは保護者の方が弓の軌道をチェックしていただき、まっすぐに動くように楽器の位置関係にも気をつけて、その都度補正していただくとよろしいです。導入期レッスンでは特に、親子二人三脚で練習に取り組んでいただく根気が大切ですね。
*小学生以上のお子さま・大人の方は、鏡を用いて弾き姿勢・弦と弓の交わり具合を丁寧にチェックし、最終的には、鏡や駒付近を直視せずとも楽譜を見続けた状態で美しいボーイングが維持できるように練習していただきます。
振動のロスを生じさせないために、楽器の水平方向の角度を維持する
水平方向の楽器の構え方・持ち方については、極力楽器が下がらないようにすることが大切です。具体的には「弦と床が水平程度」になる角度が理想的です。楽器の胴体部分が床に対して平行なとき、ネックは駒より下がっている位置関係にあるので、これではまだ不十分な角度です。
楽器が下がっている状態、床に対して弦が下がっていく方向の角度の状態では、弓は指板方向に滑っていくことになります。これは例えるなら、急勾配の下り坂に立っているような状態で、重力に負けて思ったような動作がしにくくなるのは想像に難くないでしょう。擦る位置だけでなく弓自体の重さ(約60g)や腕の重みも滑ってしまい、弦に対してそれらが効率的に伝わらなくなってしまうのです。
弦と床が水平程度の角度であれば、指板方向へと滑る力は働かなくなり、弓で擦る弦の位置を微妙に調整したりといったコントロールもできるようになります。
レッスンやご自宅での練習の際には、「譜面台の高さ」が重要になります。目線の先が楽譜の高さの中心位置よりも下がらない程度に設置することで、美しい弾き姿勢が習慣づいてきます。この姿勢を保つためには、左手で楽器を支え、あごで挟み過ぎないように、あご当てにそっとお顔(あご)を添える程度に留めることも大切です。
各弦での理想的な楽器の傾き具合を柔軟に調整する
またこれに関連して、各弦(E線~G線)をしっかりと捉えるための「楽器の傾き具合」についても考えてみましょう。ヴァイオリンは弓と弦の接点「サウンドポイント」をとらえて演奏することにより、多彩な音色を表現できる楽器です。右手の技術との兼ね合いとしても、楽器の傾き具合は大切になってきます。
E線を弾く際は、床と水平に近い形で平らに近く構えると、弓が弦に支えられているような感覚で、弓自体の重さや腕の重みが伝わりやすくなります。反対に、G線では傾き加減を増やし多めに傾けることで、それを感じることができるようになります。4弦に渡って頻繁に弓が行き来するような移弦を伴うパッセージを演奏するときには、これらの中間をとって中庸程度の傾き具合をイメージすると無理なく演奏することが可能になります。
まとめ
ヴァイオリンの持ち方・構え方と題して、ヴァイオリンの性能を最大限に発揮させるための考え方やチェックポイントをご紹介してまいりました。弦の芯を捉え、裏板からしっかりと音を鳴らすことができるようになれば、聴衆の心に届く遠くまで通る美しい音色を紡ぎ出すことができるようになります!
演奏時にあるべき理想的な姿勢として、ぜひご参考にしていただきましたら嬉しいです。
著者
稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)
コラム一覧
次の記事
<演奏時の直接音と反響音
関連記事
弦と弓の接点 -Sound Point-レッスンのご案内
ヴァイオリンレッスンについてヴァイオリン演奏時の姿勢、楽器の持ち方
華やかな音色と情緒豊かな表現力を併せ持つヴァイオリン。ソロからアンサンブル、オーケストラまで大活躍の楽器ですが、その演奏姿勢も美しくエレガント。「楽器の女王」と呼ばれる理由がここにも垣間見えますね。
弦の振動を駒を介して表板、魂柱を通じて裏板にまで伝達させ、胴体で響きを増幅させることによって、アコースティック楽器にもかかわらずまるで拡声器が持つ性質のように、広がりのある遠くまで通る音色を奏でることができます。
このような理にかなった構造の楽器が、16世紀イタリアで発明され今日まで普及していること、また、楽器自体もニコロ・アマティやガスパロ・ダ・サロなどの400年近い昔に造られたものが大切に後世に伝えられ、残されてきた...。まさに人類の宝、文化芸術遺産とも言える、ロマンあふれる楽器ですね。
拡声増幅器としてのヴァイオリンの性能を最大限に発揮するには、どのような弾き方・弾き姿勢が功を奏するでしょうか?ヴァイオリニストなら常に考え、試行錯誤して探求するテーマです。
ヴァイオリンの持ち方・構え方のチェックポイント
部分の振動を楽器の隅々にまで伝達させて豊かな響きを生み出すためには、まず振動の発生起点となる「弦の振動」を最大にすることが大切です。擦弦楽器であるヴァイオリンにとって、弓と弦の接点に生まれる摩擦力を最大にして、弦の振幅を大きくするためには、以下の点を考慮する必要があります。
- 弦と弓が直角(駒と平行)になる位置関係で楽器を構える
- 振動のロスを生じさせないために、楽器の水平方向の角度を維持する
- 各弦での理想的な楽器の傾き具合を柔軟に調整する
以下、これらのトピックについて順番に紹介していきます。
弦と弓が直角(駒と平行)になる位置関係で楽器を構える
まず、弦と弓が直角(90度)でコンタクトする状態を保つ必要があります。これは駒と弓が平行になるフォームと同じことで、弓で弦をしっかりと捉え摩擦をロスなく生み出すために、最も大切なことです。直角のフォームを実現するためには、「弓を弦に対して直角」させる考え方と、「弦を弓に対して直角」させる2つのパターンの考え方があります。
左右両方の腕の開き具合は、身体の中心線に対して「45度程度」が基本的な構え方になります。これをオーソドックスとして、左右微妙に意図的に角度を変えた構え方など、各々の奏者が経験の中から最も自然で無理の少ない演奏が実現できる角度を見出し、取り入れていく部分になります。
*小さなお子さまにとっても、これはとても大切なポイントになります。初めは保護者の方が弓の軌道をチェックしていただき、まっすぐに動くように楽器の位置関係にも気をつけて、その都度補正していただくとよろしいです。導入期レッスンでは特に、親子二人三脚で練習に取り組んでいただく根気が大切ですね。
*小学生以上のお子さま・大人の方は、鏡を用いて弾き姿勢・弦と弓の交わり具合を丁寧にチェックし、最終的には、鏡や駒付近を直視せずとも楽譜を見続けた状態で美しいボーイングが維持できるように練習していただきます。
振動のロスを生じさせないために、楽器の水平方向の角度を維持する
水平方向の楽器の構え方・持ち方については、極力楽器が下がらないようにすることが大切です。具体的には「弦と床が水平程度」になる角度が理想的です。楽器の胴体部分が床に対して平行なとき、ネックは駒より下がっている位置関係にあるので、これではまだ不十分な角度です。
楽器が下がっている状態、床に対して弦が下がっていく方向の角度の状態では、弓は指板方向に滑っていくことになります。これは例えるなら、急勾配の下り坂に立っているような状態で、重力に負けて思ったような動作がしにくくなるのは想像に難くないでしょう。擦る位置だけでなく弓自体の重さ(約60g)や腕の重みも滑ってしまい、弦に対してそれらが効率的に伝わらなくなってしまうのです。
弦と床が水平程度の角度であれば、指板方向へと滑る力は働かなくなり、弓で擦る弦の位置を微妙に調整したりといったコントロールもできるようになります。
レッスンやご自宅での練習の際には、「譜面台の高さ」が重要になります。目線の先が楽譜の高さの中心位置よりも下がらない程度に設置することで、美しい弾き姿勢が習慣づいてきます。この姿勢を保つためには、左手で楽器を支え、あごで挟み過ぎないように、あご当てにそっとお顔(あご)を添える程度に留めることも大切です。
各弦での理想的な楽器の傾き具合を柔軟に調整する
またこれに関連して、各弦(E線~G線)をしっかりと捉えるための「楽器の傾き具合」についても考えてみましょう。ヴァイオリンは弓と弦の接点「サウンドポイント」をとらえて演奏することにより、多彩な音色を表現できる楽器です。右手の技術との兼ね合いとしても、楽器の傾き具合は大切になってきます。
E線を弾く際は、床と水平に近い形で平らに近く構えると、弓が弦に支えられているような感覚で、弓自体の重さや腕の重みが伝わりやすくなります。反対に、G線では傾き加減を増やし多めに傾けることで、それを感じることができるようになります。4弦に渡って頻繁に弓が行き来するような移弦を伴うパッセージを演奏するときには、これらの中間をとって中庸程度の傾き具合をイメージすると無理なく演奏することが可能になります。
まとめ
ヴァイオリンの持ち方・構え方と題して、ヴァイオリンの性能を最大限に発揮させるための考え方やチェックポイントをご紹介してまいりました。弦の芯を捉え、裏板からしっかりと音を鳴らすことができるようになれば、聴衆の心に届く遠くまで通る美しい音色を紡ぎ出すことができるようになります!
演奏時にあるべき理想的な姿勢として、ぜひご参考にしていただきましたら嬉しいです。
著者
稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学音楽学部 弦楽器科ヴァイオリン専攻卒業。
これまでにヴァイオリンを加藤尚子、永峰高志、勅使河原真実の各氏、ヴィオラを古川原広斉氏に師事。在学中よりソロ・オーケストラなどの演奏活動、ヴァイオリン個人指導を開始。古楽器を用いたピリオド奏法、音響学の知見からの効率的な奏法を研究、演奏指導に反映させている。
一般大学卒業後、金融機関の審査担当部門に勤務。30歳手前から音楽大学に進学、特に指導教授法についても学ぶ機会を多く得てきた。
東京国際芸術協会、横浜音楽協会会員、ソノール音楽教室主宰。
コラム一覧
次の記事
<演奏時の直接音と反響音