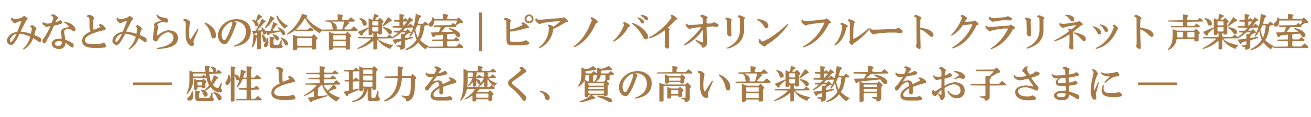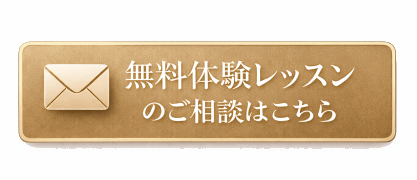左手技術の指針「フレーム」
ヴァイオリンは音程・音高を奏者自らが自在に作り出すことができる楽器です。
左手技術の重要なポイントとして、1と4の指(人差し指と小指)の位置関係が挙げられます。
1と4の指の物理的距離のことを「フレーム(または手のフレーム)」*と呼びますが、このフレームを各ポジションにおいて正確に取れるか否かが、ヴァイオリン演奏時の音程の精度に関わってきます。
具体的には、ヴァイオリンは完全5度の調弦ですので、1の指で音を取り、隣の高い方の弦を4で取った場合、オクターヴ(8度)の関係になります。同じ弦上であれば、4度です。ここで意識が必要になってくるのは、駒の方に近い位置のフレームすなわち、高いポジションを押さえるにつれて、幅が狭くなるということです。
少し専門的に捉えると、弦の振動する部分の長さ「有効弦長」はハイポジションを押さえるにつれ短くなっていきますので、フレームの幅も駒に近づく方を押さえるにつれて狭く押さえる必要があるわけです。
これらの感覚を習得していく練習に、オクターヴの音階やセヴシックOp.8の教本などがあります。当教室では、比較的早い段階からこの練習をしていただいています。
エクステンション:フレームから外れた押さえ方
むろん、フレームの感覚はオクターヴの演奏時にのみに関係してくるわけではありません。
曲中のどのようなフレーズでもあっても、この距離的感覚を正確に把握した上で弾いていけば、2と3の指(中指と薬指)はそのフレームの中で押さえることになりますし、例外的な押さえ方(1の指を低く押さえる・4の指を高く押さえるなど:エクステンション(Extension)と呼ばれます)の場合も、"ここはフレームの外に出る" というように意識して演奏することが可能になり、音程の精度は向上していきます。
1と4の指のフレームについて、音程改善の一助になりましたら幸いです。
*ヴァイオリン名教師、故イヴァン・ガラミアン氏が名付けた呼び方です。出典:『ヴァイオリン奏法と指導の原理』 ガラミアン 著/アカンサス弦楽研究会。
著者
稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)
コラム一覧
前の記事
>左手の脱力 -親指の対圧-
関連記事
ヴァイオリンの構え方レッスンのご案内
ヴァイオリンレッスンについて左手技術の指針「フレーム」
ヴァイオリンは音程・音高を奏者自らが自在に作り出すことができる楽器です。
左手技術の重要なポイントとして、1と4の指(人差し指と小指)の位置関係が挙げられます。
1と4の指の物理的距離のことを「フレーム(または手のフレーム)」*と呼びますが、このフレームを各ポジションにおいて正確に取れるか否かが、ヴァイオリン演奏時の音程の精度に関わってきます。
具体的には、ヴァイオリンは完全5度の調弦ですので、1の指で音を取り、隣の高い方の弦を4で取った場合、オクターヴ(8度)の関係になります。同じ弦上であれば、4度です。ここで意識が必要になってくるのは、駒の方に近い位置のフレームすなわち、高いポジションを押さえるにつれて、幅が狭くなるということです。
少し専門的に捉えると、弦の振動する部分の長さ「有効弦長」はハイポジションを押さえるにつれ短くなっていきますので、フレームの幅も駒に近づく方を押さえるにつれて狭く押さえる必要があるわけです。
これらの感覚を習得していく練習に、オクターヴの音階やセヴシックOp.8の教本などがあります。当教室では、比較的早い段階からこの練習をしていただいています。
エクステンション:フレームから外れた押さえ方
むろん、フレームの感覚はオクターヴの演奏時にのみに関係してくるわけではありません。
曲中のどのようなフレーズでもあっても、この距離的感覚を正確に把握した上で弾いていけば、2と3の指(中指と薬指)はそのフレームの中で押さえることになりますし、例外的な押さえ方(1の指を低く押さえる・4の指を高く押さえるなど:エクステンション(Extension)と呼ばれます)の場合も、"ここはフレームの外に出る" というように意識して演奏することが可能になり、音程の精度は向上していきます。
1と4の指のフレームについて、音程改善の一助になりましたら幸いです。
*ヴァイオリン名教師、故イヴァン・ガラミアン氏が名付けた呼び方です。出典:『ヴァイオリン奏法と指導の原理』 ガラミアン 著/アカンサス弦楽研究会。
著者
稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学 音楽学部 弦楽器科ヴァイオリン専攻卒業。
これまでにヴァイオリンを加藤尚子、永峰高志、勅使河原真実の各氏、ヴィオラを古川原広斉氏に師事。
在学中よりソロ・オーケストラなどの演奏活動に加え、ヴァイオリン個人指導を開始。
古楽器を用いたピリオド奏法や音響学の知見をもとに、効率的かつ身体に無理のない奏法を研究し、演奏および指導に反映させている。
一般大学卒業後、金融機関の審査担当部門に勤務。30歳手前より音楽大学へ進学し、演奏技術に加えて指導教授法についても体系的に学んできた。
現在は、株式会社SONOREミュージックアカデミー代表取締役として、ソノール音楽教室および出張音楽レッスンSONOREの運営・指導体制全体を統括している。
コラム一覧
前の記事
>左手の脱力 -親指の対圧-