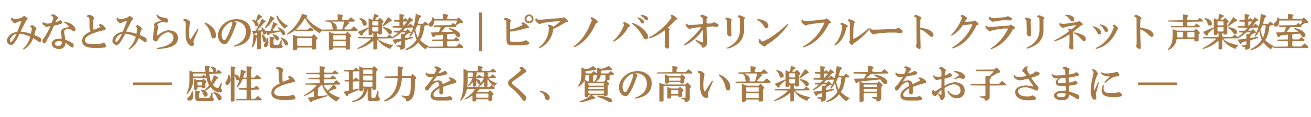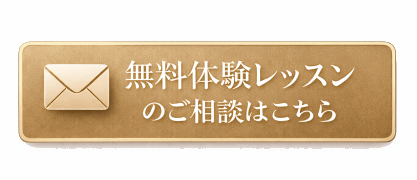ポジション移動による演奏性の向上
ヴァイオリン演奏の中級レベル以上になると、「シフティング」と呼ばれるポジション移動の技術を学ぶことになります。新しいヴァイオリン教本(鷲見三郎先生ら著)ですと、3巻の始めから登場しますね。ギターのようなフレットがないヴァイオリンにとって、ファーストポジションが各調にて音程の正確性がある程度取れるようになってきたら、「サードポジション」「セカンドポジション」の順に学習していくことになります。
ポジション移動は、4オクターブほどの広い音域を演奏することを可能にするだけでなく、弾きづらい音の並びのパッセージもポジションを臨機応変に使い分けることで弾きやすくなります。
また、弦によって異なる音色を効果的に使い分ける際にも、ポジションを変えて演奏することが必要不可欠です。ローポジションではオープンで明瞭な音色、ハイポジションではすこし籠ったような複雑な音色になると感じませんか?作曲家も意図的に「sulG(G線で演奏)」などと楽譜に表記し、指定の弦にて効果的な音色での演奏を求めることもあります。
全てのヴァイオリニストの永遠の課題
ヴァイオリンの「ポジション移動」はどのような段階であっても全てのヴァイオリニストに共通する、永遠の演奏上の課題です。以下のような悩みを感じたことはありませんか?
- ポジション移動の前後に音程が崩れる、あるいは音程が定まるまでに時間を要する
- ポジション移動時にグリッサンド(音を引きずるような連続音)が入る
- ポジション移動に時間を要し、テンポ感が崩れる
スムーズで正確な音高をつくり出すポジション移動(シフティング)を実現するには、どのようなことに気を付ければよいでしょうか?
ポジション移動の注意点・練習方法
安定したポジション移動を実現させるためには、手のフレーム感覚の習得が不可欠です。フレームについては、以前書かせていただいたこちらのコラムをぜひご覧ください。
ヴァイオリンは弦を左指で押さえることによって、弦の長さを変えて音高を作り出す楽器です。このとき注意するべきことは「ポジションが高くなるにつれて、押さえる指の幅が狭くなっていく」ということです。例えば、ローポジションであるファースト(第1)ポジションと、ハイポジションに分類されるフィフス(第5)ポジションでは、半音であっても奏者が明らかに意識しなければならないほど、指の押さえる距離的な間隔に差が出てきます。
これらのフレーム感覚を身につける練習を、網羅的に記した教本で著名なのは、「セブシックOp.8教本」です。また、「小野アンナ音階教本」や「カールフレッシュ・スケールシステム」に代表される各種音階教本でも、2オクターブ・3オクターブのスケールでは、シフティングの技術が習得できるようにまた、中・上級者になれば、和音の音階(3度・6度・8度・10度)、フラジオレットの音階まで、ポジション移動の習得と各ポジションでの正確な音程での演奏が実現できるよう、順序立て効率的に学べるように書かれています。
より身近な教本では、新しいヴァイオリン教本の第3巻の冒頭にも、ポジション移動の効果的な練習方法が記載されていますね。
ポジション移動 -具体的なチェックポイント-
ポジション移動の実際のチェックポイントとしては、以下の点に気をつける必要があります。
- 腕から手首・指先まで柔軟性を保った状態にする
- ポジション移動時に指の圧力を抜いてから、弦の表面を指先で軽く滑らせるようにして所定のポジションに到達させる
- 所定のポジションに到達してから再度、指で弦を押さえ音を出す
- ポジション移動時に右手のボーイングは、弓圧・弓速を落とす
まずは、腕から手首・指先までが柔軟性を保った状態にするということが大切です。つまり、筋肉が硬直した状態ではなく、弛緩した状態である必要があります。
その上で、ポジション移動(シフト)する際に、弦を押さえている指の圧力をいったん抜いてから、弦の表面を指先で軽く触れ、滑らせるようにして所定のポジションに到達させます。そして到達してから再度、指で弦を押さえ音を出すようにすると、音程の精度を保ったスムーズなシフティングが可能となります。*動作形状のイメージとしては、「鍵型 (ホチキスの芯のような形状 )に移動する」などと形容することが可能で、生徒の皆様にはよくお伝えしています。
また、右手もシフティング時は左手と連動する必要があります。シフト時に弓圧・弓速を落とすとポルタメントが入らずに、明瞭で音楽的表現を損なわない演奏が可能となります。※上昇系のポルタメントは音楽表現の一環として、意識的に用いられる場合もあります。
まとめ
ヴァイオリン演奏において、最も難易度の高い技術であるポジション移動。何度も練習して感覚を身につけ、音を聴き分ける正確な聴覚を養えば、演奏の表現力をぐんと上げてくれる、実に頼りになる存在になります!
このコラムをきっかけに、ぜひ積極的にポジション移動を取り入れた演奏ができるよう、ご参考になりましたら幸いです。
著者
稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)
コラム一覧
前の記事
<1と4の指のフレーム
次の記事
>ヴィブラート -指の柔軟性-
関連記事
左手の脱力 -親指の対圧-レッスンのご案内
ヴァイオリンレッスンについてポジション移動による演奏性の向上
ヴァイオリン演奏の中級レベル以上になると、「シフティング」と呼ばれるポジション移動の技術を学ぶことになります。新しいヴァイオリン教本(鷲見三郎先生ら著)ですと、3巻の始めから登場しますね。ギターのようなフレットがないヴァイオリンにとって、ファーストポジションが各調にて音程の正確性がある程度取れるようになってきたら、「サードポジション」「セカンドポジション」の順に学習していくことになります。
ポジション移動は、4オクターブほどの広い音域を演奏することを可能にするだけでなく、弾きづらい音の並びのパッセージもポジションを臨機応変に使い分けることで弾きやすくなります。
また、弦によって異なる音色を効果的に使い分ける際にも、ポジションを変えて演奏することが必要不可欠です。ローポジションではオープンで明瞭な音色、ハイポジションではすこし籠ったような複雑な音色になると感じませんか?作曲家も意図的に「sulG(G線で演奏)」などと楽譜に表記し、指定の弦にて効果的な音色での演奏を求めることもあります。
全てのヴァイオリニストの永遠の課題
ヴァイオリンの「ポジション移動」はどのような段階であっても全てのヴァイオリニストに共通する、永遠の演奏上の課題です。以下のような悩みを感じたことはありませんか?
- ポジション移動の前後に音程が崩れる、あるいは音程が定まるまでに時間を要する
- ポジション移動時にグリッサンド(音を引きずるような連続音)が入る
- ポジション移動に時間を要し、テンポ感が崩れる
スムーズで正確な音高をつくり出すポジション移動(シフティング)を実現するには、どのようなことに気を付ければよいでしょうか?
ポジション移動の注意点・練習方法
安定したポジション移動を実現させるためには、手のフレーム感覚の習得が不可欠です。フレームについては、以前書かせていただいたこちらのコラムをぜひご覧ください。
ヴァイオリンは弦を左指で押さえることによって、弦の長さを変えて音高を作り出す楽器です。このとき注意するべきことは「ポジションが高くなるにつれて、押さえる指の幅が狭くなっていく」ということです。例えば、ローポジションであるファースト(第1)ポジションと、ハイポジションに分類されるフィフス(第5)ポジションでは、半音であっても奏者が明らかに意識しなければならないほど、指の押さえる距離的な間隔に差が出てきます。
これらのフレーム感覚を身につける練習を、網羅的に記した教本で著名なのは、「セブシックOp.8教本」です。また、「小野アンナ音階教本」や「カールフレッシュ・スケールシステム」に代表される各種音階教本でも、2オクターブ・3オクターブのスケールでは、シフティングの技術が習得できるようにまた、中・上級者になれば、和音の音階(3度・6度・8度・10度)、フラジオレットの音階まで、ポジション移動の習得と各ポジションでの正確な音程での演奏が実現できるよう、順序立て効率的に学べるように書かれています。
より身近な教本では、新しいヴァイオリン教本の第3巻の冒頭にも、ポジション移動の効果的な練習方法が記載されていますね。
ポジション移動 -具体的なチェックポイント-
ポジション移動の実際のチェックポイントとしては、以下の点に気をつける必要があります。
- 腕から手首・指先まで柔軟性を保った状態にする
- ポジション移動時に指の圧力を抜いてから、弦の表面を指先で軽く滑らせるようにして所定のポジションに到達させる
- 所定のポジションに到達してから再度、指で弦を押さえ音を出す
- ポジション移動時に右手のボーイングは、弓圧・弓速を落とす
まずは、腕から手首・指先までが柔軟性を保った状態にするということが大切です。つまり、筋肉が硬直した状態ではなく、弛緩した状態である必要があります。
その上で、ポジション移動(シフト)する際に、弦を押さえている指の圧力をいったん抜いてから、弦の表面を指先で軽く触れ、滑らせるようにして所定のポジションに到達させます。そして到達してから再度、指で弦を押さえ音を出すようにすると、音程の精度を保ったスムーズなシフティングが可能となります。*動作形状のイメージとしては、「鍵型 (ホチキスの芯 のような形状 )に移動する」などと形容することが可能で、生徒の皆様にはよくお伝えしています。
また、右手もシフティング時は左手と連動する必要があります。シフト時に弓圧・弓速を落とすとポルタメントが入らずに、明瞭で音楽的表現を損なわない演奏が可能となります。※上昇系のポルタメントは音楽表現の一環として、意識的に用いられる場合もあります。
まとめ
ヴァイオリン演奏において、最も難易度の高い技術であるポジション移動。何度も練習して感覚を身につけ、音を聴き分ける正確な聴覚を養えば、演奏の表現力をぐんと上げてくれる、実に頼りになる存在になります!
このコラムをきっかけに、ぜひ積極的にポジション移動を取り入れた演奏ができるよう、ご参考になりましたら幸いです。
著者
稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学音楽学部 弦楽器科ヴァイオリン専攻卒業。
これまでにヴァイオリンを加藤尚子、永峰高志、勅使河原真実の各氏、ヴィオラを古川原広斉氏に師事。在学中よりソロ・オーケストラなどの演奏活動、ヴァイオリン個人指導を開始。古楽器を用いたピリオド奏法、音響学の知見からの効率的な奏法を研究、演奏指導に反映させている。
一般大学卒業後、金融機関の審査担当部門に勤務。30歳手前から音楽大学に進学、特に指導教授法についても学ぶ機会を多く得てきた。
東京国際芸術協会、横浜音楽協会会員、ソノール音楽教室主宰。
コラム一覧
前の記事
<1と4の指のフレーム
次の記事
>ヴィブラート -指の柔軟性-