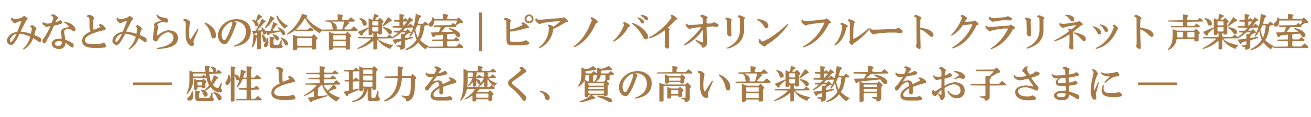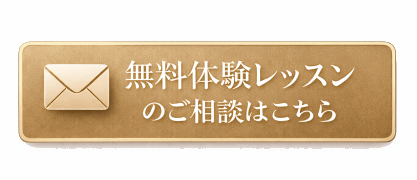フランスの作曲家ドビュッシーは新しい音楽を目指した作曲家で、印象派の画家たちから影響を受けていることはよく知られています。そんなドビュッシーが、西洋の美術だけでなく、東洋の音楽や日本の美術からもインスパイアを受けていたのです。
ドビュッシーの生涯

クロード・ドビュッシーは1862年、パリ近郊で陶器店をいとなむ家に生まれました。8歳の時に一時的にピアノを習った後、父親の知人の仲介で、ヴェルレーヌの義母にあたるモテ夫人から9歳でピアノを習います。すると彼はすぐに音楽的才能を見せ、10歳でパリ音楽院に入学します。
音楽院でドビュッシーは作曲や和声、ピアノ伴奏法なども学びます。当時のドビュッシーの夢はピアニストになることでしたが、学内のコンクールでなかなかいい成績を収めることができず、17歳にしてピアニストは諦めることになります。
この当時、作曲家を志すフランスの若者にとって、大きな登竜門が「ローマ大賞」でした。ドビュッシーもこのローマ大賞に何度も挑戦し、3回目の挑戦だった1884年についに大賞を獲得し、ローマ留学の切符を手にします。
一方、ドビュッシーはカフェや「火曜会」などでマラルメやヴェルレーヌといった象徴派の詩人や作家たちと交流するようになります。この出会いの影響はまず歌曲にあらわれ、さらにピアノ曲やオーケストラ作品にも反映されていきます。
さらにドビュッシーは、詩人や作家だけでなく、サロンにいたモネやルノワールなどの印象派の画家からも影響を受けます。ドビュッシー自身はみずから「印象派」と名乗ることはありませんでしたが、物語性を持たない、光や水などの自然を独自の手法で描こうとする彼の音楽はしだいにそう呼ばれるようになります。
【ドビュッシーの《金色の魚》】日本との出会い

「金色の魚」(ドビュッシーが所持していた蒔絵の箱)
出典:Google Arts & Culture
ヨーロッパの外の文化がたくさん入ってきた19世紀後半、ドビュッシーは従来の音楽とは違うものを作ろうと模索していました。そんな彼にとって1889年のパリ万国博覧会は、中国やジャワなど、さまざまな地域の音楽に出会うきっかけとなりました。サン=サーンスは異国の音楽に否定的な感想を持ちましたが、ドビュッシーにとってはこうした音楽、とくにジャワのガムラン音楽は衝撃的でした。
ドビュッシーは「ジャワの音楽には対位法がある」とも言い、10年以上かけて彼独自の表現に取り込んでいきました。その有名な作品が1903年のピアノ曲《版画》の中の「塔」です。ドビュッシーはこの曲でガムランに影響を受けた旋律と、五音音階を使用しています。五音音階は、その4年後に作曲されるピアノ曲《映像》第2集の「そして月は廃寺に落ちる」でも用いられています。
またこの時代、東洋の音楽だけでなく美術もヨーロッパに伝わり芸術家たちに衝撃を与えました。とくに西洋の美術の遠近法とは日本の版画は当時のフランスでもブームとなりました。このブームは「ジャポニスム」と呼ばれ、ゴッホやモネが浮世絵を題材にした作品を描いています。
ドビュッシーは「私は音楽と同じくらい絵が好きなのです」と語るくらい絵画が好きで、多くの画家とも交流していました。彼は彫刻家クローデルを通じて日本の版画に出会います。ドビュッシーは書斎に葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」を飾っていました。オーケストラのための《海-3つの交響的スケッチ-》は、この「神奈川沖浪裏」から着想を得て作曲されたものと言われていて、初版楽譜の表紙にも「神奈川沖浪裏」が使われています。
ピアノ曲でいうと、1907年に作曲された《映像》第2集の「金色の魚」が、机の上に置かれていた蒔絵の箱からドビュッシーが着想を得たと言われています。原題“Poissons
d’or“の直訳は「金の魚」ですが、金魚ではなく金粉で描かれた2匹の錦鯉です。この曲ではトリルやトレモロ、6連符や5連符がたくさん用いられ、鯉が自由に泳ぎ、それによって水面が動くさまがドビュッシーらしさで描かれています。
こうしてドビュッシーは、これまでの音楽とは違う新しい表現方法を東洋の音楽や絵画から着想を得て、彼独自の音楽を作り上げていったのです。19世紀末から20世紀初めという人や物の往来がしやすくなった時代だからこそのことだと言えるでしょう。
監修者
稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)
コラム一覧
関連記事
【レクイエムのせい?】モーツァルト最後の曲の謎当教室のご案内
ソノール音楽教室についてフランスの作曲家ドビュッシーは新しい音楽を目指した作曲家で、印象派の画家たちから影響を受けていることはよく知られています。そんなドビュッシーが、西洋の美術だけでなく、東洋の音楽や日本の美術からもインスパイアを受けていたのです。
ドビュッシーの生涯

クロード・ドビュッシーは1862年、パリ近郊で陶器店をいとなむ家に生まれました。8歳の時に一時的にピアノを習った後、父親の知人の仲介で、ヴェルレーヌの義母にあたるモテ夫人から9歳でピアノを習います。すると彼はすぐに音楽的才能を見せ、10歳でパリ音楽院に入学します。
音楽院でドビュッシーは作曲や和声、ピアノ伴奏法なども学びます。当時のドビュッシーの夢はピアニストになることでしたが、学内のコンクールでなかなかいい成績を収めることができず、17歳にしてピアニストは諦めることになります。
この当時、作曲家を志すフランスの若者にとって、大きな登竜門が「ローマ大賞」でした。ドビュッシーもこのローマ大賞に何度も挑戦し、3回目の挑戦だった1884年についに大賞を獲得し、ローマ留学の切符を手にします。
一方、ドビュッシーはカフェや「火曜会」などでマラルメやヴェルレーヌといった象徴派の詩人や作家たちと交流するようになります。この出会いの影響はまず歌曲にあらわれ、さらにピアノ曲やオーケストラ作品にも反映されていきます。
さらにドビュッシーは、詩人や作家だけでなく、サロンにいたモネやルノワールなどの印象派の画家からも影響を受けます。ドビュッシー自身はみずから「印象派」と名乗ることはありませんでしたが、物語性を持たない、光や水などの自然を独自の手法で描こうとする彼の音楽はしだいにそう呼ばれるようになります。
【ドビュッシーの《金色の魚》】日本との出会い

「金色の魚」(ドビュッシーが所持していた蒔絵の箱)
出典:Google Arts & Culture
ヨーロッパの外の文化がたくさん入ってきた19世紀後半、ドビュッシーは従来の音楽とは違うものを作ろうと模索していました。そんな彼にとって1889年のパリ万国博覧会は、中国やジャワなど、さまざまな地域の音楽に出会うきっかけとなりました。サン=サーンスは異国の音楽に否定的な感想を持ちましたが、ドビュッシーにとってはこうした音楽、とくにジャワのガムラン音楽は衝撃的でした。
ドビュッシーは「ジャワの音楽には対位法がある」とも言い、10年以上かけて彼独自の表現に取り込んでいきました。その有名な作品が1903年のピアノ曲《版画》の中の「塔」です。ドビュッシーはこの曲でガムランに影響を受けた旋律と、五音音階を使用しています。五音音階は、その4年後に作曲されるピアノ曲《映像》第2集の「そして月は廃寺に落ちる」でも用いられています。
またこの時代、東洋の音楽だけでなく美術もヨーロッパに伝わり芸術家たちに衝撃を与えました。とくに西洋の美術の遠近法とは日本の版画は当時のフランスでもブームとなりました。このブームは「ジャポニスム」と呼ばれ、ゴッホやモネが浮世絵を題材にした作品を描いています。
ドビュッシーは「私は音楽と同じくらい絵が好きなのです」と語るくらい絵画が好きで、多くの画家とも交流していました。彼は彫刻家クローデルを通じて日本の版画に出会います。ドビュッシーは書斎に葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」を飾っていました。オーケストラのための《海-3つの交響的スケッチ-》は、この「神奈川沖浪裏」から着想を得て作曲されたものと言われていて、初版楽譜の表紙にも「神奈川沖浪裏」が使われています。
ピアノ曲でいうと、1907年に作曲された《映像》第2集の「金色の魚」が、机の上に置かれていた蒔絵の箱からドビュッシーが着想を得たと言われています。原題“Poissons
d’or“の直訳は「金の魚」ですが、金魚ではなく金粉で描かれた2匹の錦鯉です。この曲ではトリルやトレモロ、6連符や5連符がたくさん用いられ、鯉が自由に泳ぎ、それによって水面が動くさまがドビュッシーらしさで描かれています。
こうしてドビュッシーは、これまでの音楽とは違う新しい表現方法を東洋の音楽や絵画から着想を得て、彼独自の音楽を作り上げていったのです。19世紀末から20世紀初めという人や物の往来がしやすくなった時代だからこそのことだと言えるでしょう。
監修者
稲葉 雅佳(主宰, ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学 音楽学部 弦楽器科ヴァイオリン専攻卒業。
これまでにヴァイオリンを加藤尚子、永峰高志、勅使河原真実の各氏、ヴィオラを古川原広斉氏に師事。
在学中よりソロ・オーケストラなどの演奏活動に加え、ヴァイオリン個人指導を開始。
古楽器を用いたピリオド奏法や音響学の知見をもとに、効率的かつ身体に無理のない奏法を研究し、演奏および指導に反映させている。
一般大学卒業後、金融機関の審査担当部門に勤務。30歳手前より音楽大学へ進学し、演奏技術に加えて指導教授法についても体系的に学んできた。
現在は、株式会社SONOREミュージックアカデミー代表取締役として、ソノール音楽教室および出張音楽レッスンSONOREの運営・指導体制全体を統括している。