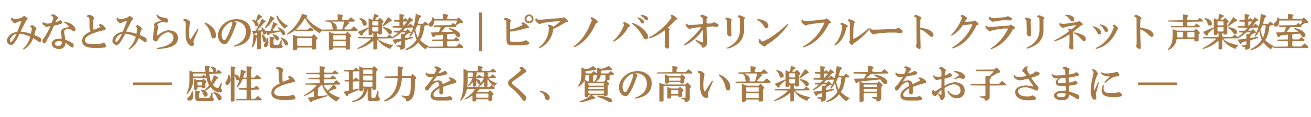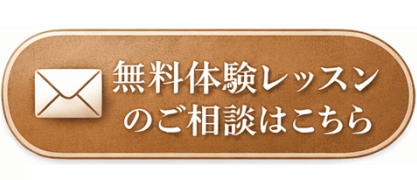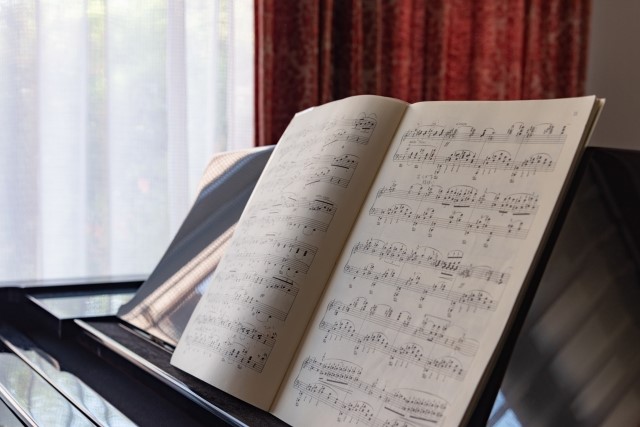
ピアノを練習したりレッスンを受ける時は、ハノンやブルグミュラーといったピアノ教本を使うことが多いですよね。
しかし、ピアノの教本といっても種類が多く、自分に適した教本を効果的に使えているか不安に思ったことはありませんか?
そこで今回のコラムでは、ピアノ教本の種類や特徴をレベル別に解説、さらに大人のピアノ初心者や独学でピアノを学びたい方におすすめの教本をご紹介します。
導入から初級におすすめのピアノ教本
まずは、ピアノ導入から初級レベルの教本をご紹介します。
ピアノに触れる前の基礎や楽譜の読み方を学ぶための教本や、簡単な練習曲が弾ける初級の教本をピックアップしました。
バーナムピアノテクニック『ミニブック』『導入書』『第1巻』
多くのピアノ指導者が支持する『バーナムピアノテクニック』には、初心者のための『ミニブック』『導入書』を含む全7シリーズの教本があります。
ここでご紹介する『ミニブック』と『導入書』は、その名の通りピアノのお稽古を始める初歩の段階で使う教本です。
『ミニブック』では、4小節の短い練習曲で音符の長さや和音の弾き方を学びます。また、音域も狭いので無理なポジション移動がなく、正しい姿勢で弾くことを習得していきます。
続いて『導入書』に進むと、グループ1〜5に分けられ1曲の長さも最大8小節。さらに、グループ4からは#や♭といった臨時記号も出てきます。
そして、ピアノ初級レベルに分類される『第1巻』では、レガートやスタッカートの弾き分けや2オクターブのスケール、半音階やペダルなど本格的なピアノテクニックの練習が始まります。
バイエル『第1巻』『第2巻』
ピアノ教本の王道である『バイエル』は、日本が高度経済成長期に一般家庭でピアノが普及し始めた時代から使われてきました。
ちなみに『バイエル』とは、フェルディナント・バイエルというドイツの作曲家の名前が由来とされています。
導入編といえる第1巻は「赤バイエル」とも呼ばれ、片手で弾く練習曲が多いです。一方、第2巻の通称「黃バイエル」では、両手の練習曲に加えて臨時記号やスケールも出てきます。
一部の練習曲には先生と生徒が連弾できる曲もあり、片手で弾きながら和音の変化を耳で感じ取る訓練にもなります。
トンプソン現代ピアノ教本『第1巻』『第2巻』
アメリカの作曲家ジョン・トンプソンが手掛けた教本。最初の段階からハ長調以外の練習曲が多く、音階や和音について学ぶことができます。
さらに、クレッシェンドやアレグロといった音楽用語もたくさん出てくるので、表現力や想像力を鍛える練習曲としても最適です。
『第1巻』は全50曲あり、曲の長さは8〜48小節と幅広くなっています。5指をすべて使うので、基本的な指使いやポジション移動を重点的に習得していきます。
『第2巻』は全60曲、ペダリングやスケール、アルペジオなどの弾き方を学び、後半には三連符やトリルといったテクニックも。ピアノ中級レベルにステップアップするための練習曲が充実した教本です。
メトードローズ『上巻』『下巻』
1901年フランスで出版された『メトードローズ』は、1951年にピアニストの安川加壽子さんの日本語翻訳版が広まり、以来『バイエル』と並びピアノ教則本として使われてきました。
『メトードローズ』の特徴は、最初から音楽的で美しい練習曲が多いこと。加えて、5本の指をすべて使う曲になっているので、バランスよく練習できます。
上巻』では、ト音記号やヘ音記号の説明や大譜表の読み方、音符の長さなどを学びます。ちなみに、幼児でも見やすいように横開きで漢字にふりがながふってある教本もありますよ。
『下巻』に進むと、長音階と短音階やレガート奏法、付点音符や指の入れ替えなどを習得していきます。全体的に親しみやすい練習曲が多いのが特徴です。
ブルグミュラー『25の練習曲』
ピアノ導入教本を終えた生徒さんに最適な『ブルグミュラー25の練習曲』。全曲にタイトルがつけられ、練習曲でありながら発表会などでも弾きやすい曲が多いです。
手が小さい子どもでも弾けるような小曲25曲で構成され、「アラベスク」「タランテラ」「貴婦人の乗馬」などが有名。ロマン派作品への入口とも言える美しい曲調が多く、大人のピアノ学習者にもおすすめです。
中級レベルにおすすめのピアノ教本
ここからは、中級レベルのピアノ教本を5つご紹介します。ピアノの基礎テクニックを身につけ、さらに高度な技術を習得するための教本をピックアップしました。
ヘラー『25の旋律的練習曲』
ハンガリー出身のピアニスト、ステファン・ヘラーが手掛けた練習曲集で、全25曲で構成されています
1曲が短く、楽譜を見ると易しそうな練習曲ですが、テクニカルで音楽的にも優れた楽曲が多いです。ロマン派音楽に通ずる練習曲といえる教本なので、ツェルニーやハノンを併用すると効果的。
クレメンティ『前奏曲と音階練習曲集』
全調性の音階練習を目的とした練習曲集で、各曲に4〜18小節の短い前奏曲が書かれています。
この前奏曲だけでも音階練習として十分な内容になっているので、ウォーミングアップにも最適です。
そして、この教本の最後には、全部の調性が含まれた音階練習の集大成といえる壮大な大練習曲があります。あまり知られていない練習曲集ですが、音階練習を強化したい方にはおすすめです。
リトルピシュナ『48の基礎練習曲集』
ハノンの併用教本として活用されることも多い『リトルピシュナ48の基礎練習曲集』は、弱い指を徹底的に鍛え、指を完全に独立させるための練習曲と言えます。
例えば、1音を抑えた状態で動く指だけでメロディを弾く練習。動かせない指につられて力が入ってしまったり、逆に保持音を弾く指が一緒に動いてしまうなど、自分の弱点に気づきやすくなります。
さらに、曲の基本形が半音ずつ上がる構成になっているので、黒鍵を弾くときのポジションや指使いも習得できるメリットがあります。
ツェルニー『30番練習曲』
ピアノレッスンの定番といえる『ツェルニー30番練習曲』は、古典ソナタを練習し始める時におすすめしたい教本です。
なぜなら、ツェルニーはベートーヴェンの弟子であり練習曲集にも大きく影響しているからです。
この30番練習曲は、古典作品を弾きこなすための基本的なテクニックが習得できるピアノ教本と言えます。また、初級の教本よりも1曲が長くなり演奏の集中力も身につきます。
ブルグミュラー『18の練習曲』
ブルグミュラー『18の練習曲』は、ペダリングやテンポルバートなど、ロマン派作品に必要なピアノテクニックの習得を目指す教本です。
この『18の練習曲』には、メロディの歌わせ方やフレーズの捉え方といった表現力の強化、音をバランスよく響かせるためのテクニックを身につける要素がたくさん詰まっています。
上級レベルにおすすめのピアノ教本
ここからは、上級レベルのピアノ教本をご紹介します。練習曲をはじめ、バロック音楽や古典の代表的な作品をピックアップしました。
バッハ『平均律クラヴィーア曲集』
バロック音楽の代表的な作曲家、バッハが残した『平均律クラヴィーア曲集』は、ピアノを専門的に学ぶ方はもちろん、鍵盤楽器を習う人にとっても重要な曲集です。
第1巻と第2巻ともに、全24の調性によるプレリュードとフーガで構成され、ピアノコンクールや音大受験では必須課題と言えます。
多声部の弾き分けや楽曲分析など、テクニックを鍛える練習曲とは異なる難しさがありますが、ピアノ上級レベルの方には取り組んで欲しい教本です。
モシュコフスキー『15の練習曲』
ツェルニー40番または50番練習曲と同レベルのモシュコフスキー『15の練習曲』は、ショパン『12の練習曲』に入る前の教本としておすすめです。
なぜなら、練習曲でありながら音楽的にも優れた楽曲が多く、効果的なペダリングや音作りなど、ロマン派作品に通ずる要素がたくさん含まれているからです。
また、各曲が長めなので、じっくり時間をかけて取り組めるのもメリットと言えます。
モシェレス『24の練習曲』
チェコ出身の作曲家、モシェレスが手掛けた『24の練習曲』は、高度なピアノテクニックの習得を目的とした曲集です。
あまり知られていない練習曲集ですが、ロマン派音楽を象徴する楽曲が多く、テクニックはもちろん表現力も鍛えられる練習曲となっています。
ちなみに『24の練習曲』は、第1番から順番に練習する必要はなく、抜粋して取り組むのもおすすめです。機械的な練習曲とは性質が異なるので、時には気分転換にもなりますよ。
ベートーヴェン『ソナタアルバム』
ピアノ学習者にとって憧れの作曲家の一人、ベートーヴェンのピアノソナタ。ベートーヴェンが生涯をかけて作曲した全32曲のソナタは、作品ごとに初期・中期・後期の3期に分けられています。
特に、三大ピアノソナタと呼ばれる『悲愴』『月光』『熱情』は、高度なピアノテクニックを要する曲ですが、音楽的にも素晴らしく壮大な楽曲です。
この3曲を含むベートーヴェンのソナタアルバムは、解説つきの国内版や海外の原典版など種類が豊富です。レッスンで使用する際は、自分のレベルや目的に適した楽譜を選ぶと良いですね。
ショパン『12の練習曲』
ピアノテクニックの最上級レベルといえるショパンの『12の練習曲』は、作品10と作品25の全24曲。
ショパンの練習曲は、洗練されたテクニックを駆使して表現力を追究するという位置づけで、単に技術を磨くだけではない音楽性に富んだ内容となっています。
楽譜は、各曲の解説や練習方法が掲載されているタイプや海外輸入版など、ベートーヴェンのピアノソナタと同様に多種多様です。
ちなみに、楽譜の出版社によって、アーティキュレーションやスラーの書き方などが大きく違うケースもあるようです。
大人のピアノ初心者や独学におすすめの教本は?
ここでは、大人のピアノ初心者や独学で学びたい方におすすめの教本をご紹介します。大人ならではの視点で、初めてでも楽しみながらピアノが学べる教本を5つピックアップしました。
ピアノの教科書
ピアノの仕組みから始まり、楽譜が読めない方でも分かりやすいピアノの入門書。本文はオールカラーで写真や図面も見やすく、ピアノ初心者の方も楽しみながら学べる教本です。
クラシックはもちろん、童謡やCM音楽など親しみやすい楽曲が掲載され、両手で演奏する喜びを感じながらテクニックを習得していきます。
さらに、各項目にはQRコードがついていて、スマホで動画を視聴することも可能です。
バスティンおとなのピアノ教本
バスティンメソッドの大人向けテキスト『バスティンおとなのピアノ教本』は、導入から基礎までを丁寧にまとめた1冊です。
ピアノの基本的なテクニックに加えて、楽典解説も散りばめられた総合的なピアノ教本で、練習曲のジャンルが幅広いのも特徴の一つ。
童謡やポップス、映画音楽など、クラシック以外にも聞き馴染みのある楽曲が多数掲載されています。
さらに、ピアノを独学で習得したい方におすすめの、教本に対応したCDつきテキストも出版されています。
大人からはじめるハノンピアノ教本
ピアノ学習者が必ず通るといっても過言ではない『ハノン』。その『ハノン』の1番〜20番を取り上げ、大人に効果的な指トレーニングを紹介しています。
単調な練習曲ではあるものの、練習のポイントや指のトレーニング方法が明確に記され、無理のないピアノ練習で上達を目指します。
大人のためのピアノレッスン
大人になって独学でピアノを学びたい方に最適な教本です。最大の特徴は、お手本動画が収録されたDVDがついていること。
テキストの説明と付属のDVDを使って、独学でもピアノの基礎から応用まで自分のペースでしっかり学べます。
そして、各セクションの課題曲には「きらきら星」や「バッハのメヌエット」といった、親しみやすいクラシックの小曲が使われています。楽譜の読み方も丁寧に書かれているので、独学でも安心して取り組めますよ。
DVD一番やさしいすぐに弾けるピアノ・レッスン
ピアノの仕組みから始まり、楽譜の読み方や指の使い方などを詳しく解説している初心者向けの教本です。
ピアノを弾く前のウォーミングアップや正しいフォームといった基礎知識も、写真やイラストで分かりやすく解説しています。
さらに、テキストの内容に沿ったDVDがついているので、独学でピアノを学びたい方にもぴったり。
まとめ
今回は、ピアノ教本の種類や特徴をレベル別にご紹介してきました。レベルが同じ教本でも、使う人の年齢やピアノを習う目的に応じて様々な選択肢があります。
ピアノの教本を選ぶ際は、自分のペースで練習が進められるよう十分に検討してみてください。
監修者
稲葉 雅佳(主宰・ヴァイオリン)
コラム一覧
前の記事
<ピアノコンクールに入賞しやすい曲とは?自由曲の選び方やおすすめの曲をご紹介
次の記事
>10歳からピアノは遅い?今からでも間に合う理由とは
関連記事
時代とともに変わるピアノ曲!バロックから近・現代までの楽曲を解説
当教室のご案内
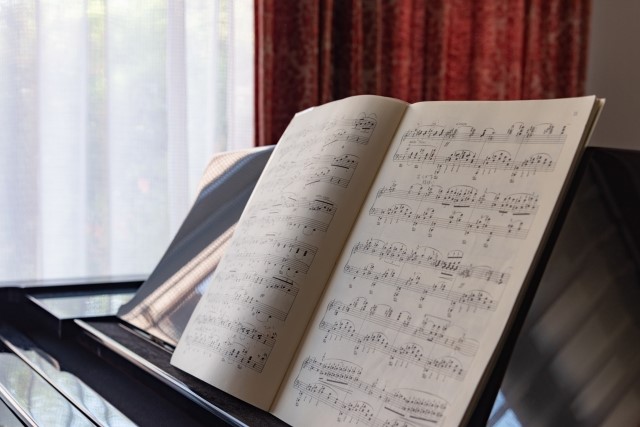
ピアノを練習したりレッスンを受ける時は、ハノンやブルグミュラーといったピアノ教本を使うことが多いですよね。
しかし、ピアノの教本といっても種類が多く、自分に適した教本を効果的に使えているか不安に思ったことはありませんか?
そこで今回のコラムでは、ピアノ教本の種類や特徴をレベル別に解説、さらに大人のピアノ初心者や独学でピアノを学びたい方におすすめの教本をご紹介します。
導入から初級におすすめのピアノ教本
まずは、ピアノ導入から初級レベルの教本をご紹介します。
ピアノに触れる前の基礎や楽譜の読み方を学ぶための教本や、簡単な練習曲が弾ける初級の教本をピックアップしました。
バーナムピアノテクニック『ミニブック』『導入書』『第1巻』
多くのピアノ指導者が支持する『バーナムピアノテクニック』には、初心者のための『ミニブック』『導入書』を含む全7シリーズの教本があります。
ここでご紹介する『ミニブック』と『導入書』は、その名の通りピアノのお稽古を始める初歩の段階で使う教本です。
『ミニブック』では、4小節の短い練習曲で音符の長さや和音の弾き方を学びます。また、音域も狭いので無理なポジション移動がなく、正しい姿勢で弾くことを習得していきます。
続いて『導入書』に進むと、グループ1〜5に分けられ1曲の長さも最大8小節。さらに、グループ4からは#や♭といった臨時記号も出てきます。
そして、ピアノ初級レベルに分類される『第1巻』では、レガートやスタッカートの弾き分けや2オクターブのスケール、半音階やペダルなど本格的なピアノテクニックの練習が始まります。
バイエル『第1巻』『第2巻』
ピアノ教本の王道である『バイエル』は、日本が高度経済成長期に一般家庭でピアノが普及し始めた時代から使われてきました。
ちなみに『バイエル』とは、フェルディナント・バイエルというドイツの作曲家の名前が由来とされています。
導入編といえる第1巻は「赤バイエル」とも呼ばれ、片手で弾く練習曲が多いです。一方、第2巻の通称「黃バイエル」では、両手の練習曲に加えて臨時記号やスケールも出てきます。
一部の練習曲には先生と生徒が連弾できる曲もあり、片手で弾きながら和音の変化を耳で感じ取る訓練にもなります。
トンプソン現代ピアノ教本『第1巻』『第2巻』
アメリカの作曲家ジョン・トンプソンが手掛けた教本。最初の段階からハ長調以外の練習曲が多く、音階や和音について学ぶことができます。
さらに、クレッシェンドやアレグロといった音楽用語もたくさん出てくるので、表現力や想像力を鍛える練習曲としても最適です。
『第1巻』は全50曲あり、曲の長さは8〜48小節と幅広くなっています。5指をすべて使うので、基本的な指使いやポジション移動を重点的に習得していきます。
『第2巻』は全60曲、ペダリングやスケール、アルペジオなどの弾き方を学び、後半には三連符やトリルといったテクニックも。ピアノ中級レベルにステップアップするための練習曲が充実した教本です。
メトードローズ『上巻』『下巻』
1901年フランスで出版された『メトードローズ』は、1951年にピアニストの安川加壽子さんの日本語翻訳版が広まり、以来『バイエル』と並びピアノ教則本として使われてきました。
『メトードローズ』の特徴は、最初から音楽的で美しい練習曲が多いこと。加えて、5本の指をすべて使う曲になっているので、バランスよく練習できます。
上巻』では、ト音記号やヘ音記号の説明や大譜表の読み方、音符の長さなどを学びます。ちなみに、幼児でも見やすいように横開きで漢字にふりがながふってある教本もありますよ。
『下巻』に進むと、長音階と短音階やレガート奏法、付点音符や指の入れ替えなどを習得していきます。全体的に親しみやすい練習曲が多いのが特徴です。
ブルグミュラー『25の練習曲』
ピアノ導入教本を終えた生徒さんに最適な『ブルグミュラー25の練習曲』。全曲にタイトルがつけられ、練習曲でありながら発表会などでも弾きやすい曲が多いです。
手が小さい子どもでも弾けるような小曲25曲で構成され、「アラベスク」「タランテラ」「貴婦人の乗馬」などが有名。ロマン派作品への入口とも言える美しい曲調が多く、大人のピアノ学習者にもおすすめです。
中級レベルにおすすめのピアノ教本
ここからは、中級レベルのピアノ教本を5つご紹介します。ピアノの基礎テクニックを身につけ、さらに高度な技術を習得するための教本をピックアップしました。
ヘラー『25の旋律的練習曲』
ハンガリー出身のピアニスト、ステファン・ヘラーが手掛けた練習曲集で、全25曲で構成されています
1曲が短く、楽譜を見ると易しそうな練習曲ですが、テクニカルで音楽的にも優れた楽曲が多いです。ロマン派音楽に通ずる練習曲といえる教本なので、ツェルニーやハノンを併用すると効果的。
クレメンティ『前奏曲と音階練習曲集』
全調性の音階練習を目的とした練習曲集で、各曲に4〜18小節の短い前奏曲が書かれています。
この前奏曲だけでも音階練習として十分な内容になっているので、ウォーミングアップにも最適です。
そして、この教本の最後には、全部の調性が含まれた音階練習の集大成といえる壮大な大練習曲があります。あまり知られていない練習曲集ですが、音階練習を強化したい方にはおすすめです。
リトルピシュナ『48の基礎練習曲集』
ハノンの併用教本として活用されることも多い『リトルピシュナ48の基礎練習曲集』は、弱い指を徹底的に鍛え、指を完全に独立させるための練習曲と言えます。
例えば、1音を抑えた状態で動く指だけでメロディを弾く練習。動かせない指につられて力が入ってしまったり、逆に保持音を弾く指が一緒に動いてしまうなど、自分の弱点に気づきやすくなります。
さらに、曲の基本形が半音ずつ上がる構成になっているので、黒鍵を弾くときのポジションや指使いも習得できるメリットがあります。
ツェルニー『30番練習曲』
ピアノレッスンの定番といえる『ツェルニー30番練習曲』は、古典ソナタを練習し始める時におすすめしたい教本です。
なぜなら、ツェルニーはベートーヴェンの弟子であり練習曲集にも大きく影響しているからです。
この30番練習曲は、古典作品を弾きこなすための基本的なテクニックが習得できるピアノ教本と言えます。また、初級の教本よりも1曲が長くなり演奏の集中力も身につきます。
ブルグミュラー『18の練習曲』
ブルグミュラー『18の練習曲』は、ペダリングやテンポルバートなど、ロマン派作品に必要なピアノテクニックの習得を目指す教本です。
この『18の練習曲』には、メロディの歌わせ方やフレーズの捉え方といった表現力の強化、音をバランスよく響かせるためのテクニックを身につける要素がたくさん詰まっています。
上級レベルにおすすめのピアノ教本
ここからは、上級レベルのピアノ教本をご紹介します。練習曲をはじめ、バロック音楽や古典の代表的な作品をピックアップしました。
バッハ『平均律クラヴィーア曲集』
バロック音楽の代表的な作曲家、バッハが残した『平均律クラヴィーア曲集』は、ピアノを専門的に学ぶ方はもちろん、鍵盤楽器を習う人にとっても重要な曲集です。
第1巻と第2巻ともに、全24の調性によるプレリュードとフーガで構成され、ピアノコンクールや音大受験では必須課題と言えます。
多声部の弾き分けや楽曲分析など、テクニックを鍛える練習曲とは異なる難しさがありますが、ピアノ上級レベルの方には取り組んで欲しい教本です。
モシュコフスキー『15の練習曲』
ツェルニー40番または50番練習曲と同レベルのモシュコフスキー『15の練習曲』は、ショパン『12の練習曲』に入る前の教本としておすすめです。
なぜなら、練習曲でありながら音楽的にも優れた楽曲が多く、効果的なペダリングや音作りなど、ロマン派作品に通ずる要素がたくさん含まれているからです。
また、各曲が長めなので、じっくり時間をかけて取り組めるのもメリットと言えます。
モシェレス『24の練習曲』
チェコ出身の作曲家、モシェレスが手掛けた『24の練習曲』は、高度なピアノテクニックの習得を目的とした曲集です。
あまり知られていない練習曲集ですが、ロマン派音楽を象徴する楽曲が多く、テクニックはもちろん表現力も鍛えられる練習曲となっています。
ちなみに『24の練習曲』は、第1番から順番に練習する必要はなく、抜粋して取り組むのもおすすめです。機械的な練習曲とは性質が異なるので、時には気分転換にもなりますよ。
ベートーヴェン『ソナタアルバム』
ピアノ学習者にとって憧れの作曲家の一人、ベートーヴェンのピアノソナタ。ベートーヴェンが生涯をかけて作曲した全32曲のソナタは、作品ごとに初期・中期・後期の3期に分けられています。
特に、三大ピアノソナタと呼ばれる『悲愴』『月光』『熱情』は、高度なピアノテクニックを要する曲ですが、音楽的にも素晴らしく壮大な楽曲です。
この3曲を含むベートーヴェンのソナタアルバムは、解説つきの国内版や海外の原典版など種類が豊富です。レッスンで使用する際は、自分のレベルや目的に適した楽譜を選ぶと良いですね。
ショパン『12の練習曲』
ピアノテクニックの最上級レベルといえるショパンの『12の練習曲』は、作品10と作品25の全24曲。
ショパンの練習曲は、洗練されたテクニックを駆使して表現力を追究するという位置づけで、単に技術を磨くだけではない音楽性に富んだ内容となっています。
楽譜は、各曲の解説や練習方法が掲載されているタイプや海外輸入版など、ベートーヴェンのピアノソナタと同様に多種多様です。
ちなみに、楽譜の出版社によって、アーティキュレーションやスラーの書き方などが大きく違うケースもあるようです。
大人のピアノ初心者や独学におすすめの教本は?
ここでは、大人のピアノ初心者や独学で学びたい方におすすめの教本をご紹介します。大人ならではの視点で、初めてでも楽しみながらピアノが学べる教本を5つピックアップしました。
ピアノの教科書
ピアノの仕組みから始まり、楽譜が読めない方でも分かりやすいピアノの入門書。本文はオールカラーで写真や図面も見やすく、ピアノ初心者の方も楽しみながら学べる教本です。
クラシックはもちろん、童謡やCM音楽など親しみやすい楽曲が掲載され、両手で演奏する喜びを感じながらテクニックを習得していきます。
さらに、各項目にはQRコードがついていて、スマホで動画を視聴することも可能です。
バスティンおとなのピアノ教本
バスティンメソッドの大人向けテキスト『バスティンおとなのピアノ教本』は、導入から基礎までを丁寧にまとめた1冊です。
ピアノの基本的なテクニックに加えて、楽典解説も散りばめられた総合的なピアノ教本で、練習曲のジャンルが幅広いのも特徴の一つ。
童謡やポップス、映画音楽など、クラシック以外にも聞き馴染みのある楽曲が多数掲載されています。
さらに、ピアノを独学で習得したい方におすすめの、教本に対応したCDつきテキストも出版されています。
大人からはじめるハノンピアノ教本
ピアノ学習者が必ず通るといっても過言ではない『ハノン』。その『ハノン』の1番〜20番を取り上げ、大人に効果的な指トレーニングを紹介しています。
単調な練習曲ではあるものの、練習のポイントや指のトレーニング方法が明確に記され、無理のないピアノ練習で上達を目指します。
大人のためのピアノレッスン
大人になって独学でピアノを学びたい方に最適な教本です。最大の特徴は、お手本動画が収録されたDVDがついていること。
テキストの説明と付属のDVDを使って、独学でもピアノの基礎から応用まで自分のペースでしっかり学べます。
そして、各セクションの課題曲には「きらきら星」や「バッハのメヌエット」といった、親しみやすいクラシックの小曲が使われています。楽譜の読み方も丁寧に書かれているので、独学でも安心して取り組めますよ。
DVD一番やさしいすぐに弾けるピアノ・レッスン
ピアノの仕組みから始まり、楽譜の読み方や指の使い方などを詳しく解説している初心者向けの教本です。
ピアノを弾く前のウォーミングアップや正しいフォームといった基礎知識も、写真やイラストで分かりやすく解説しています。
さらに、テキストの内容に沿ったDVDがついているので、独学でピアノを学びたい方にもぴったり。
まとめ
今回は、ピアノ教本の種類や特徴をレベル別にご紹介してきました。レベルが同じ教本でも、使う人の年齢やピアノを習う目的に応じて様々な選択肢があります。
ピアノの教本を選ぶ際は、自分のペースで練習が進められるよう十分に検討してみてください。
監修者
稲葉 雅佳(主宰・ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学音楽学部 弦楽器科ヴァイオリン専攻卒業。
これまでにヴァイオリンを加藤尚子、永峰高志、勅使河原真実の各氏、ヴィオラを古川原広斉氏に師事。在学中よりソロ・オーケストラなどの演奏活動、ヴァイオリン個人指導を開始。古楽器を用いたピリオド奏法、音響学の知見からの効率的な奏法を研究、演奏指導に反映させている。
一般大学卒業後、金融機関の審査担当部門に勤務。30歳手前から音楽大学に進学、特に指導教授法についても学ぶ機会を多く得てきた。
東京国際芸術協会、横浜音楽協会会員、ソノール音楽教室主宰。
コラム一覧
前の記事
<ピアノコンクールに入賞しやすい曲とは?自由曲の選び方やおすすめの曲をご紹介
次の記事
>
関連記事
時代とともに変わるピアノ曲!バロックから近・現代までの楽曲を解説
当教室のご案内