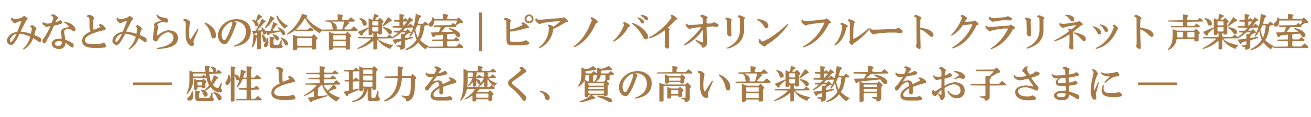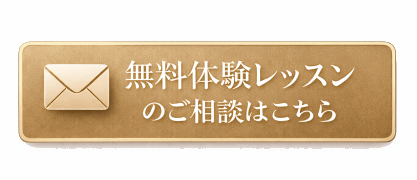ピアノを弾いていて、離れた鍵盤への跳躍が苦手という方は多いのではないでしょうか。特に子供の生徒さんや、大人から始めた方にとって、跳躍は技術的なハードルの一つです。
跳躍がうまくできないと、せっかく練習した曲も本番で失敗してしまう可能性があります。
しかし、正しいコツと練習方法を身につければ、跳躍は確実に上達できる技術です。
この記事では、ピアノの跳躍を成功させるための具体的なコツから、練習のポイント、さらには本番での対処法まで詳しく解説します。
お子様の練習をサポートしたい親御様や、ご自身で上達を目指す大人の方にとって、実践的なアドバイスをお届けします
ピアノの跳躍を外さないための3つのコツ
跳躍を成功させるためには、基本的なコツを理解することが重要です。こちらでは、跳躍を成功させる論理的なアプローチについて紹介します。
視線を先に送る
跳躍で最も大切なのは、実際に手を動かす前に「目で先に着地点を確認する」ことです。多くの初心者は手の動きと同時に視線を移動させてしまいがちですが、これでは正確な跳躍は困難です。
まず楽譜を見て次に弾く音を確認したら、実際にその鍵盤の位置を目で捉えてから手を移動させましょう。
この「視線の先行」により、脳が正確な距離と方向を計算し、手の動きをガイドしてくれます。練習時は意識的にゆっくりと視線移動を行い、この感覚を身に付けることが大切です。
黒鍵や基準音で位置を決める
跳躍の着地点を正確に捉えるには、鍵盤上の目印となるポイントを活用することが効果的です。特に黒鍵は視覚的に分かりやすい目印となります。
例えば、遠くのドを狙う際は「ドの右隣にある黒鍵2つのグループ」を目印にしたり、ファを狙う際は「ファとソの間の黒鍵」を基準にしたりします。
また、オクターブ関係にある同じ音名の鍵盤を基準音として使うことも有効です。普段から鍵盤上のランドマークを意識して練習することで、跳躍時の位置感覚が向上します。
肩と肘で運び手首で着地する
跳躍の動作は「運搬」と「着地」の2つの段階に分けて考えると理解しやすくなります。まず肩と肘を使って手を目的地まで「運び」、最後に手首で微調整しながら「着地」させます。
運搬段階では、肩を軸とした大きな動きで手全体を移動させましょう。この時、手首に力を入れすぎないことが重要です。
着地段階では、手首を柔軟に使って鍵盤との接触をコントロールします。この2段階の動作を意識することで、力みすぎて音がかたくなったり、逆に弱すぎて音が出なかったりすることを防げます。
ピアノの跳躍が安定しない原因と練習のポイント
跳躍が安定しない場合、多くは練習方法に課題があることが多いです。効率的な練習のアプローチを知ることで、着実に技術を向上させられます。
動作を分けて個別に鍛える
跳躍を一度に完成させようとするのではなく、まず動作を要素に分解して練習することが重要です。まずは「視線移動」だけを練習し、次に「手の移動軌道」、そして「着地のコントロール」といったように、段階的にアプローチしましょう。
視線移動の練習では、楽譜を見ずに鍵盤だけを見ながら、目で跳躍先を確認してから手を動かします。手の移動軌道の練習では、実際に音を出さずに空中で手の動きだけを繰り返し、正しい軌道を体に覚えさせます。
着地のコントロール練習では、跳躍先の鍵盤に手を置いた状態から、様々な強さで音を出す練習を行いましょう。
成功率でテンポと距離を上げる
跳躍の練習では、成功率を基準にして段階的に難易度を上げることが効果的です。まず近距離の跳躍を10回中9回成功できるようになってから、より遠い距離にチャレンジします。同様に、ゆっくりとしたテンポで確実にできるようになってから、徐々にテンポを上げていきます。
この段階的なアプローチにより、技術が確実に定着し、本番でのミスを大幅に減らせるでしょう。焦って難しい跳躍ばかり練習するよりも、基礎的な跳躍の成功率を高める方が、最終的には高度な技術習得につながります。
ランダム化と両手化で仕上げる
基本的な跳躍ができるようになったら、より実践的な練習に移行します。ランダム化とは、決まった順序ではなく、様々な跳躍パターンを無作為に組み合わせて練習することです。これにより、楽曲の中で突然現れる跳躍にも対応できる応用力が身に付きます。
両手化の練習では、片手ずつ完璧にできる跳躍を、両手で同時に行います。左右の手が異なる方向や距離に跳躍する場合もあるため、両手の協調性を高める練習は不可欠です。メトロノームを使用して、両手の跳躍タイミングを正確に合わせる練習も効果的です。
速いテンポや本番で跳躍が崩れる原因と対策
練習では成功する跳躍も、本番になると失敗してしまうことがあります。これには心理的な要因と技術的な要因の両方が関わっています。
重心と呼吸を整える
本番の緊張により、無意識に体が硬くなってしまうことが跳躍失敗の大きな原因です。特に重心が不安定になると、跳躍の精度が大幅に低下します。演奏前には座る位置を確認し、両足をしっかりと床につけて安定した重心を作ります。
また、呼吸も重要な要素です。跳躍の前に息を止めてしまうと、体全体が緊張して正確な動作ができなくなります。跳躍前に軽く息を吸い、跳躍動作と共に自然に息を吐くことを意識しましょう。この呼吸のリズムを、普段の練習から身に付けておくことが大切です。
前腕回旋と手首のしなりを同期させる
速いテンポでの跳躍では、前腕の回旋運動と手首のしなりを同期させることが重要です。前腕回旋とは、肘を軸とした前腕のねじり運動のことで、これを手首の上下運動と組み合わせることで、無駄な力を使わずに効率的な跳躍が可能になります。
この同期した動作により、跳躍時の衝撃が分散され、着地も柔らかくコントロールできます。まず前腕回旋だけを意識した跳躍、次に手首のしなりだけを意識した跳躍を行い、最後に両方を組み合わせて練習しましょう。
視線・動作・リズムを一本化する
本番で跳躍を成功させるには、視線移動、手の動作、音楽のリズムを一体化させることが必要です。練習段階では別々に考えていたこれらの要素を、統合的にコントロールできるようになることが目標です。
この一本化を実現するには、メトロノームに合わせて「視線移動のタイミング」「跳躍開始のタイミング」「着地のタイミング」を正確に合わせる練習が効果的です。慣れてきたら、メトロノームなしでも同様のタイミング感を維持できるように練習します。
本番で跳躍をミスしたときに立て直す方法
どれだけ練習しても、本番でミスが起こる可能性はゼロではありません。ミスをした後にどう立て直すかが重要なので、こちらで解説します。
誤音を止めてすぐ次に置く
跳躍でミスをしてしまった場合、まず誤って押してしまった鍵盤から素早く手を離すことが重要です。誤音を長く響かせてしまうと、観客にミスがより強く印象づけられてしまいます。
手を離したら、慌てずに正しい鍵盤の位置を確認し、次の音を正確に置きます。このとき、ミスを取り返そうと焦って力んでしまうと、さらなるミスを誘発しやすいです。深呼吸をして、普段の練習通りの動作で次の音に移行することを心がけましょう。
拍を取り戻して次小節で合流する
跳躍のミスにより音楽の流れが乱れてしまった場合は、無理に元の拍に戻ろうとせず、次の小節の頭で音楽の流れに合流することを目指します。カウントを続け、正しい拍の位置を把握し続けることが重要です。
ピアノソロの場合は、次の自然な区切りまで演奏を続けて音楽の流れを取り戻します。伴奏の場合は、歌や他の楽器に合わせて、次の小節から正常な演奏に戻ることを優先します。完璧を求めすぎず、音楽全体の流れを大切にする姿勢が重要です。
連続跳躍は簡略化して戻す
複数の跳躍が連続する箇所でミスをした場合、全ての跳躍を完璧に演奏しようとするとさらなるミスを招く可能性があります。このような状況では、一時的に演奏を簡略化して音楽の流れを維持することが賢明です。
例えば、両手での跳躍が難しい場合は片手に集中したり、複雑な跳躍パターンをより単純な形に変更したりします。重要なのは、音楽が完全に止まってしまうことを避け、観客に演奏が継続していることを印象付けることです。
ピアノの跳躍練習におすすめの曲選び
跳躍技術の向上には、段階的に適切な楽曲を選んで練習することが重要です。レベルに応じた楽曲選択により、効率的に技術を身に付けられます。
基礎を作る曲を選ぶ
跳躍練習の基礎作りには、比較的近距離の跳躍が含まれた楽曲から始めることが重要です。初心者におすすめなのは、バイエル後半やブルクミュラー25の練習曲です。特にブルクミュラーの「アラベスク」や「牧歌」は、基本的な跳躍パターンを学ぶのに適しています。
チェルニー100番の中には、様々な距離の跳躍が含まれた練習曲があり、段階的に技術を向上させられます。
これらの楽曲では、正確性を重視してゆっくりとしたテンポから練習を始め、確実にできるようになってからテンポを上げることが大切です。クラシック以外では、映画音楽やポップスのピアノアレンジの中にも、基礎的な跳躍練習に適した楽曲があります。
実戦で鍛える曲を取り入れる
基礎が身に付いたら、より実践的な跳躍が含まれた楽曲に挑戦します。ソナチネアルバムの楽曲や、ショパンのワルツなどは、様々な跳躍パターンを含んでおり、実戦的な練習に適しています。
モーツァルトのピアノソナタも跳躍練習には効果的です。特にK.545やK.331は適度な難易度の跳躍が含まれています。
これらの楽曲では、音楽的な表現と技術的な正確性の両方が求められます。そのため、単純な技術練習を超えた総合的な能力が身に付くでしょう。
高難度の曲で耐性を仕上げる
跳躍技術の仕上げとして、高難度の楽曲にも挑戦してみましょう。リストのハンガリー狂詩曲やショパンのエチュードなどは、極めて技術的に要求の高い跳躍が含まれています。これらの楽曲を練習することで、どのような跳躍にも対応できる技術的な耐性が身に付きます。
ただし、高難度の楽曲に挑戦する際は、無理をせず、十分な基礎技術が身に付いてからチャレンジすることが重要です。
指導者がいる場合は、適切なタイミングでの楽曲選択についてアドバイスを求めることをおすすめします。独学の場合は、録画や録音で自分の演奏を客観的にチェックし、技術的な課題を把握することが大切です。
ピアノの跳躍のコツを学んで練習しよう
本記事では、ピアノの跳躍で失敗しないための練習方法やコツをわかりやすく解説しました。
ピアノの跳躍は、正しいコツと段階的な練習により必ず上達できる技術です。視線の先行、基準点の活用、動作の分解といった基本的なアプローチから、本番での対処法まで、幅広い知識をつけて練習しましょう。
跳躍技術は一朝一夕には身に付きませんが、正しい方法で継続的に練習すれば、必ず結果は現れます。
ソノール音楽教室では、個々の生徒さんのレベルに応じた指導を行っており、技術向上をしっかりとサポートします。ピアノを習ってみたい方や独学で伸び悩んでいる方は、ぜひ専門的な指導を受けながら、確実な技術向上を目指してください。
監修者
稲葉 雅佳(主宰・ヴァイオリン)
コラム一覧
前の記事
<10歳からピアノは遅い?今からでも間に合う理由とは
次の記事
>アップライトか電子ピアノはどっち?目的に合わせた失敗しない選び方を解説
関連記事
発表会でおすすめのピアノ曲は?初級から上級まで聴き映えする楽曲を解説
当教室のご案内

ピアノを弾いていて、離れた鍵盤への跳躍が苦手という方は多いのではないでしょうか。特に子供の生徒さんや、大人から始めた方にとって、跳躍は技術的なハードルの一つです。
跳躍がうまくできないと、せっかく練習した曲も本番で失敗してしまう可能性があります。
しかし、正しいコツと練習方法を身につければ、跳躍は確実に上達できる技術です。
この記事では、ピアノの跳躍を成功させるための具体的なコツから、練習のポイント、さらには本番での対処法まで詳しく解説します。
お子様の練習をサポートしたい親御様や、ご自身で上達を目指す大人の方にとって、実践的なアドバイスをお届けします
ピアノの跳躍を外さないための3つのコツ
跳躍を成功させるためには、基本的なコツを理解することが重要です。こちらでは、跳躍を成功させる論理的なアプローチについて紹介します。
視線を先に送る
跳躍で最も大切なのは、実際に手を動かす前に「目で先に着地点を確認する」ことです。多くの初心者は手の動きと同時に視線を移動させてしまいがちですが、これでは正確な跳躍は困難です。
まず楽譜を見て次に弾く音を確認したら、実際にその鍵盤の位置を目で捉えてから手を移動させましょう。
この「視線の先行」により、脳が正確な距離と方向を計算し、手の動きをガイドしてくれます。練習時は意識的にゆっくりと視線移動を行い、この感覚を身に付けることが大切です。
黒鍵や基準音で位置を決める
跳躍の着地点を正確に捉えるには、鍵盤上の目印となるポイントを活用することが効果的です。特に黒鍵は視覚的に分かりやすい目印となります。
例えば、遠くのドを狙う際は「ドの右隣にある黒鍵2つのグループ」を目印にしたり、ファを狙う際は「ファとソの間の黒鍵」を基準にしたりします。
また、オクターブ関係にある同じ音名の鍵盤を基準音として使うことも有効です。普段から鍵盤上のランドマークを意識して練習することで、跳躍時の位置感覚が向上します。
肩と肘で運び手首で着地する
跳躍の動作は「運搬」と「着地」の2つの段階に分けて考えると理解しやすくなります。まず肩と肘を使って手を目的地まで「運び」、最後に手首で微調整しながら「着地」させます。
運搬段階では、肩を軸とした大きな動きで手全体を移動させましょう。この時、手首に力を入れすぎないことが重要です。
着地段階では、手首を柔軟に使って鍵盤との接触をコントロールします。この2段階の動作を意識することで、力みすぎて音がかたくなったり、逆に弱すぎて音が出なかったりすることを防げます。
ピアノの跳躍が安定しない原因と練習のポイント
跳躍が安定しない場合、多くは練習方法に課題があることが多いです。効率的な練習のアプローチを知ることで、着実に技術を向上させられます。
動作を分けて個別に鍛える
跳躍を一度に完成させようとするのではなく、まず動作を要素に分解して練習することが重要です。まずは「視線移動」だけを練習し、次に「手の移動軌道」、そして「着地のコントロール」といったように、段階的にアプローチしましょう。
視線移動の練習では、楽譜を見ずに鍵盤だけを見ながら、目で跳躍先を確認してから手を動かします。手の移動軌道の練習では、実際に音を出さずに空中で手の動きだけを繰り返し、正しい軌道を体に覚えさせます。
着地のコントロール練習では、跳躍先の鍵盤に手を置いた状態から、様々な強さで音を出す練習を行いましょう。
成功率でテンポと距離を上げる
跳躍の練習では、成功率を基準にして段階的に難易度を上げることが効果的です。まず近距離の跳躍を10回中9回成功できるようになってから、より遠い距離にチャレンジします。同様に、ゆっくりとしたテンポで確実にできるようになってから、徐々にテンポを上げていきます。
この段階的なアプローチにより、技術が確実に定着し、本番でのミスを大幅に減らせるでしょう。焦って難しい跳躍ばかり練習するよりも、基礎的な跳躍の成功率を高める方が、最終的には高度な技術習得につながります。
ランダム化と両手化で仕上げる
基本的な跳躍ができるようになったら、より実践的な練習に移行します。ランダム化とは、決まった順序ではなく、様々な跳躍パターンを無作為に組み合わせて練習することです。これにより、楽曲の中で突然現れる跳躍にも対応できる応用力が身に付きます。
両手化の練習では、片手ずつ完璧にできる跳躍を、両手で同時に行います。左右の手が異なる方向や距離に跳躍する場合もあるため、両手の協調性を高める練習は不可欠です。メトロノームを使用して、両手の跳躍タイミングを正確に合わせる練習も効果的です。
速いテンポや本番で跳躍が崩れる原因と対策
練習では成功する跳躍も、本番になると失敗してしまうことがあります。これには心理的な要因と技術的な要因の両方が関わっています。
重心と呼吸を整える
本番の緊張により、無意識に体が硬くなってしまうことが跳躍失敗の大きな原因です。特に重心が不安定になると、跳躍の精度が大幅に低下します。演奏前には座る位置を確認し、両足をしっかりと床につけて安定した重心を作ります。
また、呼吸も重要な要素です。跳躍の前に息を止めてしまうと、体全体が緊張して正確な動作ができなくなります。跳躍前に軽く息を吸い、跳躍動作と共に自然に息を吐くことを意識しましょう。この呼吸のリズムを、普段の練習から身に付けておくことが大切です。
前腕回旋と手首のしなりを同期させる
速いテンポでの跳躍では、前腕の回旋運動と手首のしなりを同期させることが重要です。前腕回旋とは、肘を軸とした前腕のねじり運動のことで、これを手首の上下運動と組み合わせることで、無駄な力を使わずに効率的な跳躍が可能になります。
この同期した動作により、跳躍時の衝撃が分散され、着地も柔らかくコントロールできます。まず前腕回旋だけを意識した跳躍、次に手首のしなりだけを意識した跳躍を行い、最後に両方を組み合わせて練習しましょう。
視線・動作・リズムを一本化する
本番で跳躍を成功させるには、視線移動、手の動作、音楽のリズムを一体化させることが必要です。練習段階では別々に考えていたこれらの要素を、統合的にコントロールできるようになることが目標です。
この一本化を実現するには、メトロノームに合わせて「視線移動のタイミング」「跳躍開始のタイミング」「着地のタイミング」を正確に合わせる練習が効果的です。慣れてきたら、メトロノームなしでも同様のタイミング感を維持できるように練習します。
本番で跳躍をミスしたときに立て直す方法
どれだけ練習しても、本番でミスが起こる可能性はゼロではありません。ミスをした後にどう立て直すかが重要なので、こちらで解説します。
誤音を止めてすぐ次に置く
跳躍でミスをしてしまった場合、まず誤って押してしまった鍵盤から素早く手を離すことが重要です。誤音を長く響かせてしまうと、観客にミスがより強く印象づけられてしまいます。
手を離したら、慌てずに正しい鍵盤の位置を確認し、次の音を正確に置きます。このとき、ミスを取り返そうと焦って力んでしまうと、さらなるミスを誘発しやすいです。深呼吸をして、普段の練習通りの動作で次の音に移行することを心がけましょう。
拍を取り戻して次小節で合流する
跳躍のミスにより音楽の流れが乱れてしまった場合は、無理に元の拍に戻ろうとせず、次の小節の頭で音楽の流れに合流することを目指します。カウントを続け、正しい拍の位置を把握し続けることが重要です。
ピアノソロの場合は、次の自然な区切りまで演奏を続けて音楽の流れを取り戻します。伴奏の場合は、歌や他の楽器に合わせて、次の小節から正常な演奏に戻ることを優先します。完璧を求めすぎず、音楽全体の流れを大切にする姿勢が重要です。
連続跳躍は簡略化して戻す
複数の跳躍が連続する箇所でミスをした場合、全ての跳躍を完璧に演奏しようとするとさらなるミスを招く可能性があります。このような状況では、一時的に演奏を簡略化して音楽の流れを維持することが賢明です。
例えば、両手での跳躍が難しい場合は片手に集中したり、複雑な跳躍パターンをより単純な形に変更したりします。重要なのは、音楽が完全に止まってしまうことを避け、観客に演奏が継続していることを印象付けることです。
ピアノの跳躍練習におすすめの曲選び
跳躍技術の向上には、段階的に適切な楽曲を選んで練習することが重要です。レベルに応じた楽曲選択により、効率的に技術を身に付けられます。
基礎を作る曲を選ぶ
跳躍練習の基礎作りには、比較的近距離の跳躍が含まれた楽曲から始めることが重要です。初心者におすすめなのは、バイエル後半やブルクミュラー25の練習曲です。特にブルクミュラーの「アラベスク」や「牧歌」は、基本的な跳躍パターンを学ぶのに適しています。
チェルニー100番の中には、様々な距離の跳躍が含まれた練習曲があり、段階的に技術を向上させられます。
これらの楽曲では、正確性を重視してゆっくりとしたテンポから練習を始め、確実にできるようになってからテンポを上げることが大切です。クラシック以外では、映画音楽やポップスのピアノアレンジの中にも、基礎的な跳躍練習に適した楽曲があります。
実戦で鍛える曲を取り入れる
基礎が身に付いたら、より実践的な跳躍が含まれた楽曲に挑戦します。ソナチネアルバムの楽曲や、ショパンのワルツなどは、様々な跳躍パターンを含んでおり、実戦的な練習に適しています。
モーツァルトのピアノソナタも跳躍練習には効果的です。特にK.545やK.331は適度な難易度の跳躍が含まれています。
これらの楽曲では、音楽的な表現と技術的な正確性の両方が求められます。そのため、単純な技術練習を超えた総合的な能力が身に付くでしょう。
高難度の曲で耐性を仕上げる
跳躍技術の仕上げとして、高難度の楽曲にも挑戦してみましょう。リストのハンガリー狂詩曲やショパンのエチュードなどは、極めて技術的に要求の高い跳躍が含まれています。これらの楽曲を練習することで、どのような跳躍にも対応できる技術的な耐性が身に付きます。
ただし、高難度の楽曲に挑戦する際は、無理をせず、十分な基礎技術が身に付いてからチャレンジすることが重要です。
指導者がいる場合は、適切なタイミングでの楽曲選択についてアドバイスを求めることをおすすめします。独学の場合は、録画や録音で自分の演奏を客観的にチェックし、技術的な課題を把握することが大切です。
ピアノの跳躍のコツを学んで練習しよう
本記事では、ピアノの跳躍で失敗しないための練習方法やコツをわかりやすく解説しました。
ピアノの跳躍は、正しいコツと段階的な練習により必ず上達できる技術です。視線の先行、基準点の活用、動作の分解といった基本的なアプローチから、本番での対処法まで、幅広い知識をつけて練習しましょう。
跳躍技術は一朝一夕には身に付きませんが、正しい方法で継続的に練習すれば、必ず結果は現れます。
ソノール音楽教室では、個々の生徒さんのレベルに応じた指導を行っており、技術向上をしっかりとサポートします。ピアノを習ってみたい方や独学で伸び悩んでいる方は、ぜひ専門的な指導を受けながら、確実な技術向上を目指してください。
監修者
稲葉 雅佳(主宰・ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学音楽学部 弦楽器科ヴァイオリン専攻卒業。
これまでにヴァイオリンを加藤尚子、永峰高志、勅使河原真実の各氏、ヴィオラを古川原広斉氏に師事。在学中よりソロ・オーケストラなどの演奏活動、ヴァイオリン個人指導を開始。古楽器を用いたピリオド奏法、音響学の知見からの効率的な奏法を研究、演奏指導に反映させている。
一般大学卒業後、金融機関の審査担当部門に勤務。30歳手前から音楽大学に進学、特に指導教授法についても学ぶ機会を多く得てきた。
東京国際芸術協会、横浜音楽協会会員、ソノール音楽教室主宰。
コラム一覧
前の記事
<10歳からピアノは遅い?今からでも間に合う理由とは
次の記事
>アップライトか電子ピアノはどっち?目的に合わせた失敗しない選び方を解説
関連記事
発表会でおすすめのピアノ曲は?初級から上級まで聴き映えする楽曲を解説