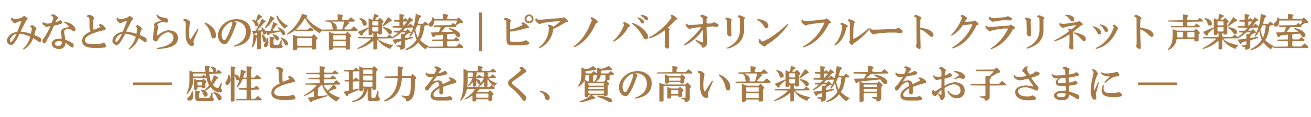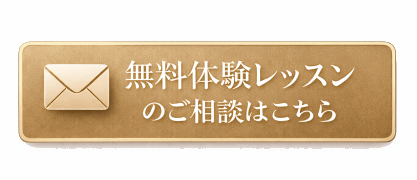「子どもにピアノを習わせたいけれどアップライトと電子ピアノ、どちらを買う?」
「夜しか練習時間が取れないから電子ピアノかな…でも、本当にそれで上達できる?」
ピアノを始めようと決めた瞬間から、多くの方がこんな悩みを抱えています。価格も機能も大きく違う2つのピアノ。
選び方を間違えると、せっかくの練習意欲が削がれてしまったり、後から買い替えが必要になったりすることも。
この記事では、アップライトピアノと電子ピアノの本質的な違いから、あなたの目的や環境にぴったり合った選び方まで、プロの視点で徹底解説します。
失敗しない楽器選びで、充実したピアノライフをスタートさせましょう。
アップライトと電子ピアノの違い
ピアノを始めたいと思ったとき、多くの方が悩むのが「アップライトピアノ」と「電子ピアノ」のどちらを選ぶかという問題です。
まずは、それぞれの特徴をしっかり理解した上で、自分の目的や環境に合った選択をすることが大切です。
ここでは、アップライトピアノと電子ピアノの本質的な違いについて詳しく見ていきましょう。
生音と電子音
アップライトピアノと電子ピアノの最も根本的な違いは、音の発生メカニズムにあります。
アップライトピアノは、鍵盤を押すとハンマーが弦を打って音を出すアコースティック楽器です。
弦の振動が響板に伝わり、楽器全体が共鳴することで豊かな音色が生まれます。この生音は、打鍵の強さやタッチの微妙な違いによって無限に近い音色の変化を生み出すことができ、倍音成分も豊富に含まれています。
一方、電子ピアノは、鍵盤の動きをセンサーで検知し、あらかじめ録音・プログラムされた音源をスピーカーから再生する電子楽器です。
音の発生に物理的な弦や響板は使用せず、デジタル処理によって音を作り出します。そのため、アップライトピアノのような自然な残響や音の広がりを完全に再現することは難しく、倍音成分の複雑さにも差が生じます。
ただし、近年の高品質な電子ピアノでは、グランドピアノの音をサンプリングし、打鍵の強弱に応じた音色変化を再現する技術が向上しました。
そのため、十分に練習用として活用できるレベルに達していると言えます。
ハンマー機構と鍵盤構造
先ほどもお伝えした通り、アップライトピアノの鍵盤は、複雑なアクション機構によって動いているのが特徴です。
鍵盤を押すとハンマーが弦を打ち、一定の深さまで押し込むとエスケープメント機構が働き、ハンマーが弦から離れます。
この機構により、鍵盤を押し切った状態でもハンマーは自由に動けるため、連打が可能になります。
また、鍵盤を離すとダンパーが弦に戻り、音が止まる仕組みです。この構造により、指先のコントロールが直接音に反映され、奏者の意図した表現が可能になります。
鍵盤の戻りも重力とバネの力を利用した物理的なものなので、速いパッセージでの連打性能に優れています。
対して電子ピアノは、鍵盤の動きを光学センサーや接点センサーで検知して音を鳴らす方式です。
物理的なハンマーと弦の接触はないため、エスケープメント機構そのものは存在しませんが、上位機種ではこの感触を模した「エスケープメント機構付き鍵盤」を採用しているモデルもあります。
センサー方式には1センサー、2センサー、3センサーがあり、センサー数が多いほど鍵盤の動きを細かく検知でき、連打性や表現力が向上します。
また、鍵盤内部におもりを配置して重さを調整したり、木製鍵盤を採用することで、アコースティックピアノに近いタッチ感を実現しようとしている機種もあるのが特徴です。
ただし、物理的なハンマーと弦の相互作用を完全に再現することは構造上困難であり、微妙なタッチの違いによる音色変化の幅は、アコースティックピアノに比べると限定的です。
機能面
機能面での違いも、選択時の重要なポイントになります。アップライトピアノは基本的に音を出すことに特化した楽器で、付加機能はほとんどありません。
ただし、サイレント機能付きモデルも存在し、ハンマーが弦を打つ直前で止め、電子音で演奏できる機能を備えています。
この場合、ヘッドホンを使えば夜間練習も可能になりますが、通常のアコースティックモードとサイレントモードではタッチ感が若干異なる点に注意が必要です。
また、アップライトピアノは定期的な調律などのメンテナンスが不可欠で、ランニングコストがかかります。
対して電子ピアノは、ヘッドホン端子による消音機能が標準装備されているほか、多彩な機能を備えています。
内蔵メトロノーム、演奏の録音機能、レッスン曲の再生、さまざまな音色の切り替え、USB端子やBluetooth接続によるスマートフォン・タブレット・パソコンとの連携など、練習をサポートする機能が豊富です。
MIDI出力に対応していれば、作曲や音楽制作にも活用できます。また、調律が不要でメンテナンスコストが低く、温度や湿度の影響も受けにくいため、管理が容易です。
ただし、電子機器であるため経年劣化や故障のリスクがあり、古いモデルでは修理部品の入手が困難になる場合もあります。
アップライトと電子ピアノ、どっちを選ぶ?目的別の選び方
ここまで、両者の特徴をみてきましたが、ここからはどちらを選ぶのがおすすめかをわかりやすく解説していきます。
アップライトを選ぶのがおすすめな場合
まずは、どのような場面でアップライトを選ぶといいかをみていきましょう。
クラシックの基礎を定着させる
クラシックピアノの基礎をしっかりと身につけたい場合は、アップライトピアノが最適です。
クラシック音楽では、指先のタッチによる繊細な音色のコントロールや、ペダルを使った音の響きの調整が重要な表現技法となります。
アップライトピアノは、鍵盤を押す速度や深さ、指の重さのかけ方によって音色が無段階に変化するため、タッチによる表現力を自然に習得できます。
将来的に本格的なクラシックピアノを目指すなら、最初からアップライトピアノで練習することで、正しいタッチと表現力の基礎を築くことができるでしょう。
音色コントロールを重視する
音色コントロール能力を高めたい方にも、アップライトピアノがおすすめです。
アコースティックピアノは、打鍵の瞬間の速度や角度、指の形、体重のかけ方など、演奏者の動作すべてが音に反映されます。
同じ音量でも、柔らかく温かみのある音、明るく輝かしい音、鋭く切れ味のある音など、無限の音色を作り出すことが可能です。
このような音色の違いは、弦の振動の仕方や倍音成分の変化によって生まれるもので、アコースティック楽器特有の現象です。
日常的にこの感覚を養うことで、「この場面ではこういう音が欲しい」という音楽的な判断力と、それを実現する技術の両方が育つでしょう。
受験や発表会を見据えている
音楽系の高校や大学の受験、コンクール・発表会などで本番を見据えている方には、アップライトピアノでの練習が不可欠です。
これらの本番では必ずグランドピアノやアップライトピアノといったアコースティックピアノが使用されるため、自宅でも同じ環境で練習することが理想的です。
電子ピアノで練習していると、本番のピアノとのタッチの違いや音の響き方の違いに戸惑い、本来の力を発揮できないことがあります。
特に鍵盤の重さ、連打のスピード、ペダルの効き方は、電子ピアノとアコースティックピアノで大きく異なるため、注意が必要です。
電子ピアノを選ぶのがおすすめな場合
続いて、電子ピアノを選ぶ方がよい場合を紹介します。
夜間練習や防音を優先する
集合住宅に住んでいる方や、夜間に練習時間を確保したい方には、電子ピアノが現実的な選択肢です。
アップライトピアノは消音機能付きモデルを除き、演奏時の音が周囲に響くため、時間帯や住宅環境によっては近隣への配慮が必要になります。
防音対策として防音室を設置する方法もありますが、数十万円から数百万円の費用がかかり、設置スペースも必要です。
その点電子ピアノであれば、ヘッドホンを使用することで完全に消音でき、深夜や早朝でも周囲を気にせず練習できるのが魅力です。
ピアノ演奏をお試しする
「ピアノを始めてみたいけれど、続けられるか分からない」「まずは気軽に試してみたい」という方には、電子ピアノから始めることをおすすめします。
アップライトピアノは購入費用が高額なうえ、設置後の移動も難しく、万が一続かなかった場合の処分にも手間とコストがかかります。
電子ピアノなら比較的手頃な価格で購入でき、引っ越しや部屋の模様替えの際も移動が容易です。
また、内蔵されているメトロノームやレッスン曲、録音機能などは、独学で始める方にとって心強いサポートツールになるでしょう。
アップライトの上手な選び方
ここからは、アップライトピアノを選ぶ際に気にしておきたいポイントを紹介します。
予算に合わせて選ぶ
アップライトピアノの予算を考える際は、本体価格だけでなく、搬入費用、調律費用、サイレント機能の有無など、総額で検討することが重要です。
新品のアップライトピアノは、国産メーカーのエントリーモデルで50万円前後から、上位モデルでは100万円以上になります。海外メーカーのものはさらに高額になることもあります。
中古ピアノであれば20万円程度から購入可能ですが、状態によっては全面修理が必要な場合もあるため、信頼できる専門店で購入することが大切です。
搬入費用は、階段の有無やエレベーターの大きさ、搬入経路の複雑さによって2万円から10万円以上かかることもあります。
また、年1回程度の調律費用も継続的に必要なことを覚えておきましょう。
サイズと設置で選ぶ
アップライトピアノの設置には、楽器本体のサイズに加えて、周囲に必要なスペースや環境条件を考慮する必要があります。
一般的なアップライトピアノの幅は約150cm、奥行きは約60cm、高さは110〜130cm程度です。
また設置の際は、壁から10cm以上離すことが推奨されています。さらに、直射日光が当たる場所や、エアコンの風が直接当たる場所は避けましょう。
弾き心地(タッチ)で選ぶ
アップライトピアノを選ぶ際、弾き心地は最も重要な判断基準の1つです。
実際に店頭で試奏し、複数台を弾き比べることをおすすめします。
まず確認したいのは、鍵盤の重さです。重すぎると指が疲れやすく、子どもや初心者には負担が大きくなりますが、軽すぎるとコントロールが難しく、表現力を養いにくくなります。
次に、鍵盤を離したときの戻りがスムーズかどうかを確認しましょう。連打やトリルなど速いパッセージを弾いたときに、鍵盤がすぐに元の位置に戻らないと演奏に支障が出ます。
また、すべての鍵盤で音の大きさや音色が均一に揃っているかも重要なポイントです。低音から高音まで弾いてみて、極端に音が小さい鍵盤や、音色が違う鍵盤がないかチェックしましょう。
好みの弾き心地のピアノを用意できれば、練習も楽しくなりますよ。
電子ピアノの上手な選び方
電子ピアノは価格帯が幅広く、機能や性能も多岐にわたります。自分の目的と予算に合った一台を見つけるために、優先すべきポイントを明確にしましょう。
予算に合わせて選ぶ
電子ピアノの価格帯は、エントリーモデルの5万円前後から、プロ仕様の50万円以上まで幅広く展開されています。
5万円〜10万円の入門モデルでも、88鍵フルサイズで基本的な練習には十分ですが、鍵盤の材質は樹脂製で、センサーは2センサー程度、ペダルはオン・オフの単純なスイッチ式が一般的です。
15万円〜25万円の中級モデルになると、木製鍵盤や3センサー方式、エスケープメント機構付き鍵盤、ハーフペダル対応など、よりアコースティックピアノに近い機能が搭載されます。
30万円以上の上位モデルでは、グランドピアノの鍵盤構造を忠実に再現した機構や、高品質なスピーカーシステム、リアルな音源などが採用されています。
総合的に試算し、自分の練習レベルと将来の目標に見合った機種を選びましょう。
本物っぽい弾き心地で選ぶ
電子ピアノでアコースティックピアノに近い弾き心地を求めるなら、鍵盤の材質と構造に注目しましょう。
木製鍵盤は樹脂製に比べて指へのフィット感が良く、吸湿性もあるため長時間の演奏でも滑りにくいという利点があります。
鍵盤の長さも重要で、アコースティックピアノと同じ長さの鍵盤は、奥を弾いたときと手前を弾いたときの重さの違いを自然に再現できます。
ペダルについては、ハーフペダル対応モデルを選ぶことで、踏み込み具合による響きの微妙な調整が可能になり、表現力が大きく広がるでしょう。
機能性で選ぶ
電子ピアノには多彩な機能が搭載されていますが、実際に毎日使う機能を厳選して選ぶことが大切です。
まず、内蔵メトロノームは練習の必需品で、テンポを正確に保つ訓練に欠かせません。音量調整機能や拍子の変更ができるモデルも便利です。
録音機能は、自分の演奏を客観的に聴き直すことで、リズムの乱れや音のバランスの悪さに気づくことができ、上達を早めます。
内蔵メモリーだけでなく、USBメモリーやスマートフォンに録音できる機種もあります。
Bluetooth接続やUSB接続は、スマートフォン・タブレットのピアノ学習アプリと連携でき、楽譜表示や運指ガイド、レッスン動画との同期など、学習の幅を広げてくれるでしょう。
自分にとって本当に必要な機能に絞って選ぶことで、コストパフォーマンスの良い選択ができます。
ピアノを上達させるにはアップライトがおすすめ!初心者向け練習方法
アップライトピアノを手に入れたら、その特性を活かした効果的な練習方法で、着実に上達を目指しましょう。ここでは、初心者がアップライトピアノで練習する際のポイントを紹介します。
ゆっくり弾いて指と音のつながりをつくる
アップライトピアノでの練習では、まず「ゆっくり弾くこと」が基本です。
速く弾きたい気持ちを抑えて、テンポを落として一音一音を丁寧に確認しながら弾きましょう。
ゆっくり弾くことで、指の動きと出てくる音の関係を意識でき、弱音から強音まで自分がどれだけコントロールできているかを確認できます。
また、ペダルの踏みはじめから戻すまでの動作も、ゆっくりした演奏の中で確認しましょう。
ペダルを踏むタイミングが早すぎると音が濁り、遅すぎると切れてしまいます。ゆっくりしたテンポで正確なペダリングを身につけることで、速い曲でも自然に対応できるようになります。
15分×2回の短い練習をくり返す
長時間の練習よりも、短時間の練習を複数回に分けて行う方が、効率的に上達できておすすめです。
特に初心者のうちは、集中力が続く15分程度の練習を、朝と夜の2回に分けて行うといいでしょう。
<おすすめの練習内容>
● スケール練習
● スタッカート練習
● 曲の中から1フレーズを取り出し繰り返し練習
1回の練習で曲全体を通そうとせず、難しい部分や苦手な部分を集中的に攻略することが上達の近道です。
このようなルーティンを毎日継続することで、指の筋力と柔軟性が向上し、楽譜を読む力も自然についていきます。
レッスンと録音でズレを見つけて直す
独学だけでは気づきにくい癖やリズムのズレも、週1回のレッスンと自宅での録音を組み合わせることで、客観的に発見し修正できます。
レッスンでは、先生が耳で聴いて指摘してくれるポイントをチェックし、次回までの練習課題として取り組みましょう。
自宅では、スマートフォンやICレコーダーで自分の演奏を録音し、聴き直すことが効果的です。
自分で弾いているときには気づかなかったリズムの乱れや、音の強弱のつけすぎ・つけなさすぎ、ペダルの濁りなどが、録音を聴くとはっきりと分かります。
レッスンでのプロの指導と、自宅での客観的な自己チェックを繰り返すことで、着実に演奏技術が磨かれていきます。
ピアノを上達させるならソノール音楽教室へ!
アップライトピアノと電子ピアノ、どちらを選ぶか迷ったときは、実際に両方を弾き比べてみることが一番の近道です。
そして、プロの講師から直接アドバイスを受けることで、自分に最適な選択ができるようになります。
横浜市西区みなとみらい駅から徒歩3分のソノール音楽教室では、音響にこだわった残響設計のレッスン室で、アコースティックピアノのタッチと響きを実際に体験できるのが魅力です。
経験豊富な現役演奏家の講師陣が、一人ひとりの目的やレベルに合わせた丁寧な指導を行い、正しいタッチの習得からペダルワークまで、基礎から応用まで幅広くサポートいたします。
「ピアノを始めてみたいけれど、どの楽器を選べばいいか分からない」「子どもにピアノを習わせたいが、何から始めればいいか迷っている」という方は、まずは無料体験レッスンにお越しください。
監修者
稲葉 雅佳(主宰・ヴァイオリン)
コラム一覧
前の記事
<ピアノの跳躍を失敗しないコツ!練習方法やおすすめの練習曲を紹介
次の記事
>
関連記事
発表会でおすすめのピアノ曲は?初級から上級まで聴き映えする楽曲を解説
当教室のご案内

「子どもにピアノを習わせたいけれどアップライトと電子ピアノ、どちらを買う?」
「夜しか練習時間が取れないから電子ピアノかな…でも、本当にそれで上達できる?」
ピアノを始めようと決めた瞬間から、多くの方がこんな悩みを抱えています。価格も機能も大きく違う2つのピアノ。
選び方を間違えると、せっかくの練習意欲が削がれてしまったり、後から買い替えが必要になったりすることも。
この記事では、アップライトピアノと電子ピアノの本質的な違いから、あなたの目的や環境にぴったり合った選び方まで、プロの視点で徹底解説します。
失敗しない楽器選びで、充実したピアノライフをスタートさせましょう。
アップライトと電子ピアノの違い
ピアノを始めたいと思ったとき、多くの方が悩むのが「アップライトピアノ」と「電子ピアノ」のどちらを選ぶかという問題です。
まずは、それぞれの特徴をしっかり理解した上で、自分の目的や環境に合った選択をすることが大切です。
ここでは、アップライトピアノと電子ピアノの本質的な違いについて詳しく見ていきましょう。
生音と電子音
アップライトピアノと電子ピアノの最も根本的な違いは、音の発生メカニズムにあります。
アップライトピアノは、鍵盤を押すとハンマーが弦を打って音を出すアコースティック楽器です。
弦の振動が響板に伝わり、楽器全体が共鳴することで豊かな音色が生まれます。この生音は、打鍵の強さやタッチの微妙な違いによって無限に近い音色の変化を生み出すことができ、倍音成分も豊富に含まれています。
一方、電子ピアノは、鍵盤の動きをセンサーで検知し、あらかじめ録音・プログラムされた音源をスピーカーから再生する電子楽器です。
音の発生に物理的な弦や響板は使用せず、デジタル処理によって音を作り出します。そのため、アップライトピアノのような自然な残響や音の広がりを完全に再現することは難しく、倍音成分の複雑さにも差が生じます。
ただし、近年の高品質な電子ピアノでは、グランドピアノの音をサンプリングし、打鍵の強弱に応じた音色変化を再現する技術が向上しました。
そのため、十分に練習用として活用できるレベルに達していると言えます。
ハンマー機構と鍵盤構造
先ほどもお伝えした通り、アップライトピアノの鍵盤は、複雑なアクション機構によって動いているのが特徴です。
鍵盤を押すとハンマーが弦を打ち、一定の深さまで押し込むとエスケープメント機構が働き、ハンマーが弦から離れます。
この機構により、鍵盤を押し切った状態でもハンマーは自由に動けるため、連打が可能になります。
また、鍵盤を離すとダンパーが弦に戻り、音が止まる仕組みです。この構造により、指先のコントロールが直接音に反映され、奏者の意図した表現が可能になります。
鍵盤の戻りも重力とバネの力を利用した物理的なものなので、速いパッセージでの連打性能に優れています。
対して電子ピアノは、鍵盤の動きを光学センサーや接点センサーで検知して音を鳴らす方式です。
物理的なハンマーと弦の接触はないため、エスケープメント機構そのものは存在しませんが、上位機種ではこの感触を模した「エスケープメント機構付き鍵盤」を採用しているモデルもあります。
センサー方式には1センサー、2センサー、3センサーがあり、センサー数が多いほど鍵盤の動きを細かく検知でき、連打性や表現力が向上します。
また、鍵盤内部におもりを配置して重さを調整したり、木製鍵盤を採用することで、アコースティックピアノに近いタッチ感を実現しようとしている機種もあるのが特徴です。
ただし、物理的なハンマーと弦の相互作用を完全に再現することは構造上困難であり、微妙なタッチの違いによる音色変化の幅は、アコースティックピアノに比べると限定的です。
機能面
機能面での違いも、選択時の重要なポイントになります。アップライトピアノは基本的に音を出すことに特化した楽器で、付加機能はほとんどありません。
ただし、サイレント機能付きモデルも存在し、ハンマーが弦を打つ直前で止め、電子音で演奏できる機能を備えています。
この場合、ヘッドホンを使えば夜間練習も可能になりますが、通常のアコースティックモードとサイレントモードではタッチ感が若干異なる点に注意が必要です。
また、アップライトピアノは定期的な調律などのメンテナンスが不可欠で、ランニングコストがかかります。
対して電子ピアノは、ヘッドホン端子による消音機能が標準装備されているほか、多彩な機能を備えています。
内蔵メトロノーム、演奏の録音機能、レッスン曲の再生、さまざまな音色の切り替え、USB端子やBluetooth接続によるスマートフォン・タブレット・パソコンとの連携など、練習をサポートする機能が豊富です。
MIDI出力に対応していれば、作曲や音楽制作にも活用できます。また、調律が不要でメンテナンスコストが低く、温度や湿度の影響も受けにくいため、管理が容易です。
ただし、電子機器であるため経年劣化や故障のリスクがあり、古いモデルでは修理部品の入手が困難になる場合もあります。
アップライトと電子ピアノ、どっちを選ぶ?目的別の選び方
ここまで、両者の特徴をみてきましたが、ここからはどちらを選ぶのがおすすめかをわかりやすく解説していきます。
アップライトを選ぶのがおすすめな場合
まずは、どのような場面でアップライトを選ぶといいかをみていきましょう。
クラシックの基礎を定着させる
クラシックピアノの基礎をしっかりと身につけたい場合は、アップライトピアノが最適です。
クラシック音楽では、指先のタッチによる繊細な音色のコントロールや、ペダルを使った音の響きの調整が重要な表現技法となります。
アップライトピアノは、鍵盤を押す速度や深さ、指の重さのかけ方によって音色が無段階に変化するため、タッチによる表現力を自然に習得できます。
将来的に本格的なクラシックピアノを目指すなら、最初からアップライトピアノで練習することで、正しいタッチと表現力の基礎を築くことができるでしょう。
音色コントロールを重視する
音色コントロール能力を高めたい方にも、アップライトピアノがおすすめです。
アコースティックピアノは、打鍵の瞬間の速度や角度、指の形、体重のかけ方など、演奏者の動作すべてが音に反映されます。
同じ音量でも、柔らかく温かみのある音、明るく輝かしい音、鋭く切れ味のある音など、無限の音色を作り出すことが可能です。
このような音色の違いは、弦の振動の仕方や倍音成分の変化によって生まれるもので、アコースティック楽器特有の現象です。
日常的にこの感覚を養うことで、「この場面ではこういう音が欲しい」という音楽的な判断力と、それを実現する技術の両方が育つでしょう。
受験や発表会を見据えている
音楽系の高校や大学の受験、コンクール・発表会などで本番を見据えている方には、アップライトピアノでの練習が不可欠です。
これらの本番では必ずグランドピアノやアップライトピアノといったアコースティックピアノが使用されるため、自宅でも同じ環境で練習することが理想的です。
電子ピアノで練習していると、本番のピアノとのタッチの違いや音の響き方の違いに戸惑い、本来の力を発揮できないことがあります。
特に鍵盤の重さ、連打のスピード、ペダルの効き方は、電子ピアノとアコースティックピアノで大きく異なるため、注意が必要です。
電子ピアノを選ぶのがおすすめな場合
続いて、電子ピアノを選ぶ方がよい場合を紹介します。
夜間練習や防音を優先する
集合住宅に住んでいる方や、夜間に練習時間を確保したい方には、電子ピアノが現実的な選択肢です。
アップライトピアノは消音機能付きモデルを除き、演奏時の音が周囲に響くため、時間帯や住宅環境によっては近隣への配慮が必要になります。
防音対策として防音室を設置する方法もありますが、数十万円から数百万円の費用がかかり、設置スペースも必要です。
その点電子ピアノであれば、ヘッドホンを使用することで完全に消音でき、深夜や早朝でも周囲を気にせず練習できるのが魅力です。
ピアノ演奏をお試しする
「ピアノを始めてみたいけれど、続けられるか分からない」「まずは気軽に試してみたい」という方には、電子ピアノから始めることをおすすめします。
アップライトピアノは購入費用が高額なうえ、設置後の移動も難しく、万が一続かなかった場合の処分にも手間とコストがかかります。
電子ピアノなら比較的手頃な価格で購入でき、引っ越しや部屋の模様替えの際も移動が容易です。
また、内蔵されているメトロノームやレッスン曲、録音機能などは、独学で始める方にとって心強いサポートツールになるでしょう。
アップライトの上手な選び方
ここからは、アップライトピアノを選ぶ際に気にしておきたいポイントを紹介します。
予算に合わせて選ぶ
アップライトピアノの予算を考える際は、本体価格だけでなく、搬入費用、調律費用、サイレント機能の有無など、総額で検討することが重要です。
新品のアップライトピアノは、国産メーカーのエントリーモデルで50万円前後から、上位モデルでは100万円以上になります。海外メーカーのものはさらに高額になることもあります。
中古ピアノであれば20万円程度から購入可能ですが、状態によっては全面修理が必要な場合もあるため、信頼できる専門店で購入することが大切です。
搬入費用は、階段の有無やエレベーターの大きさ、搬入経路の複雑さによって2万円から10万円以上かかることもあります。
また、年1回程度の調律費用も継続的に必要なことを覚えておきましょう。
サイズと設置で選ぶ
アップライトピアノの設置には、楽器本体のサイズに加えて、周囲に必要なスペースや環境条件を考慮する必要があります。
一般的なアップライトピアノの幅は約150cm、奥行きは約60cm、高さは110〜130cm程度です。
また設置の際は、壁から10cm以上離すことが推奨されています。さらに、直射日光が当たる場所や、エアコンの風が直接当たる場所は避けましょう。
弾き心地(タッチ)で選ぶ
アップライトピアノを選ぶ際、弾き心地は最も重要な判断基準の1つです。
実際に店頭で試奏し、複数台を弾き比べることをおすすめします。
まず確認したいのは、鍵盤の重さです。重すぎると指が疲れやすく、子どもや初心者には負担が大きくなりますが、軽すぎるとコントロールが難しく、表現力を養いにくくなります。
次に、鍵盤を離したときの戻りがスムーズかどうかを確認しましょう。連打やトリルなど速いパッセージを弾いたときに、鍵盤がすぐに元の位置に戻らないと演奏に支障が出ます。
また、すべての鍵盤で音の大きさや音色が均一に揃っているかも重要なポイントです。低音から高音まで弾いてみて、極端に音が小さい鍵盤や、音色が違う鍵盤がないかチェックしましょう。
好みの弾き心地のピアノを用意できれば、練習も楽しくなりますよ。
電子ピアノの上手な選び方
電子ピアノは価格帯が幅広く、機能や性能も多岐にわたります。自分の目的と予算に合った一台を見つけるために、優先すべきポイントを明確にしましょう。
予算に合わせて選ぶ
電子ピアノの価格帯は、エントリーモデルの5万円前後から、プロ仕様の50万円以上まで幅広く展開されています。
5万円〜10万円の入門モデルでも、88鍵フルサイズで基本的な練習には十分ですが、鍵盤の材質は樹脂製で、センサーは2センサー程度、ペダルはオン・オフの単純なスイッチ式が一般的です。
15万円〜25万円の中級モデルになると、木製鍵盤や3センサー方式、エスケープメント機構付き鍵盤、ハーフペダル対応など、よりアコースティックピアノに近い機能が搭載されます。
30万円以上の上位モデルでは、グランドピアノの鍵盤構造を忠実に再現した機構や、高品質なスピーカーシステム、リアルな音源などが採用されています。
総合的に試算し、自分の練習レベルと将来の目標に見合った機種を選びましょう。
本物っぽい弾き心地で選ぶ
電子ピアノでアコースティックピアノに近い弾き心地を求めるなら、鍵盤の材質と構造に注目しましょう。
木製鍵盤は樹脂製に比べて指へのフィット感が良く、吸湿性もあるため長時間の演奏でも滑りにくいという利点があります。
鍵盤の長さも重要で、アコースティックピアノと同じ長さの鍵盤は、奥を弾いたときと手前を弾いたときの重さの違いを自然に再現できます。
ペダルについては、ハーフペダル対応モデルを選ぶことで、踏み込み具合による響きの微妙な調整が可能になり、表現力が大きく広がるでしょう。
機能性で選ぶ
電子ピアノには多彩な機能が搭載されていますが、実際に毎日使う機能を厳選して選ぶことが大切です。
まず、内蔵メトロノームは練習の必需品で、テンポを正確に保つ訓練に欠かせません。音量調整機能や拍子の変更ができるモデルも便利です。
録音機能は、自分の演奏を客観的に聴き直すことで、リズムの乱れや音のバランスの悪さに気づくことができ、上達を早めます。
内蔵メモリーだけでなく、USBメモリーやスマートフォンに録音できる機種もあります。
Bluetooth接続やUSB接続は、スマートフォン・タブレットのピアノ学習アプリと連携でき、楽譜表示や運指ガイド、レッスン動画との同期など、学習の幅を広げてくれるでしょう。
自分にとって本当に必要な機能に絞って選ぶことで、コストパフォーマンスの良い選択ができます。
ピアノを上達させるにはアップライトがおすすめ!初心者向け練習方法
アップライトピアノを手に入れたら、その特性を活かした効果的な練習方法で、着実に上達を目指しましょう。ここでは、初心者がアップライトピアノで練習する際のポイントを紹介します。
ゆっくり弾いて指と音のつながりをつくる
アップライトピアノでの練習では、まず「ゆっくり弾くこと」が基本です。
速く弾きたい気持ちを抑えて、テンポを落として一音一音を丁寧に確認しながら弾きましょう。
ゆっくり弾くことで、指の動きと出てくる音の関係を意識でき、弱音から強音まで自分がどれだけコントロールできているかを確認できます。
また、ペダルの踏みはじめから戻すまでの動作も、ゆっくりした演奏の中で確認しましょう。
ペダルを踏むタイミングが早すぎると音が濁り、遅すぎると切れてしまいます。ゆっくりしたテンポで正確なペダリングを身につけることで、速い曲でも自然に対応できるようになります。
15分×2回の短い練習をくり返す
長時間の練習よりも、短時間の練習を複数回に分けて行う方が、効率的に上達できておすすめです。
特に初心者のうちは、集中力が続く15分程度の練習を、朝と夜の2回に分けて行うといいでしょう。
<おすすめの練習内容>
● スケール練習
● スタッカート練習
● 曲の中から1フレーズを取り出し繰り返し練習
1回の練習で曲全体を通そうとせず、難しい部分や苦手な部分を集中的に攻略することが上達の近道です。
このようなルーティンを毎日継続することで、指の筋力と柔軟性が向上し、楽譜を読む力も自然についていきます。
レッスンと録音でズレを見つけて直す
独学だけでは気づきにくい癖やリズムのズレも、週1回のレッスンと自宅での録音を組み合わせることで、客観的に発見し修正できます。
レッスンでは、先生が耳で聴いて指摘してくれるポイントをチェックし、次回までの練習課題として取り組みましょう。
自宅では、スマートフォンやICレコーダーで自分の演奏を録音し、聴き直すことが効果的です。
自分で弾いているときには気づかなかったリズムの乱れや、音の強弱のつけすぎ・つけなさすぎ、ペダルの濁りなどが、録音を聴くとはっきりと分かります。
レッスンでのプロの指導と、自宅での客観的な自己チェックを繰り返すことで、着実に演奏技術が磨かれていきます。
ピアノを上達させるならソノール音楽教室へ!
アップライトピアノと電子ピアノ、どちらを選ぶか迷ったときは、実際に両方を弾き比べてみることが一番の近道です。
そして、プロの講師から直接アドバイスを受けることで、自分に最適な選択ができるようになります。
横浜市西区みなとみらい駅から徒歩3分のソノール音楽教室では、音響にこだわった残響設計のレッスン室で、アコースティックピアノのタッチと響きを実際に体験できるのが魅力です。
経験豊富な現役演奏家の講師陣が、一人ひとりの目的やレベルに合わせた丁寧な指導を行い、正しいタッチの習得からペダルワークまで、基礎から応用まで幅広くサポートいたします。
「ピアノを始めてみたいけれど、どの楽器を選べばいいか分からない」「子どもにピアノを習わせたいが、何から始めればいいか迷っている」という方は、まずは無料体験レッスンにお越しください。
監修者
稲葉 雅佳(主宰・ヴァイオリン)

洗足学園音楽大学音楽学部 弦楽器科ヴァイオリン専攻卒業。
これまでにヴァイオリンを加藤尚子、永峰高志、勅使河原真実の各氏、ヴィオラを古川原広斉氏に師事。在学中よりソロ・オーケストラなどの演奏活動、ヴァイオリン個人指導を開始。古楽器を用いたピリオド奏法、音響学の知見からの効率的な奏法を研究、演奏指導に反映させている。
一般大学卒業後、金融機関の審査担当部門に勤務。30歳手前から音楽大学に進学、特に指導教授法についても学ぶ機会を多く得てきた。
東京国際芸術協会、横浜音楽協会会員、ソノール音楽教室主宰。
コラム一覧
前の記事
<ピアノの跳躍を失敗しないコツ!練習方法やおすすめの練習曲を紹介
次の記事
>
関連記事
発表会でおすすめのピアノ曲は?初級から上級まで聴き映えする楽曲を解説